© ONE LOVE All Rights reserved.
- HOME
- 応援アンバサダー
ONE LOVE 応援アンバサダー
-

大阪公立大学 / 現代システム科学研究科
伊藤 嘉余子 教授
保護者の病気や入院、経済的困難や虐待、育児放棄などさまざまな理由によって家庭で暮らせない子どもを社会で養育することを「社会的養護」といいます。
社会的養護には大きく「施設での養育」と「里親など家庭での養育」があります。子ども虐待や社会的養護、里親などに興味があるけれど、よくわからないという人、里親をやってみたいという気持ちはあるけど、あと一歩が踏み出せない人、里親にはなれないけれど、困っている子どもや里親を応援したいなと思う人、子どもや子育てに関心のあるさまざまな人がここでつながり、交流できたら、もっと笑顔の里親、子ども、家族が増えるのではないかと期待しています。 -
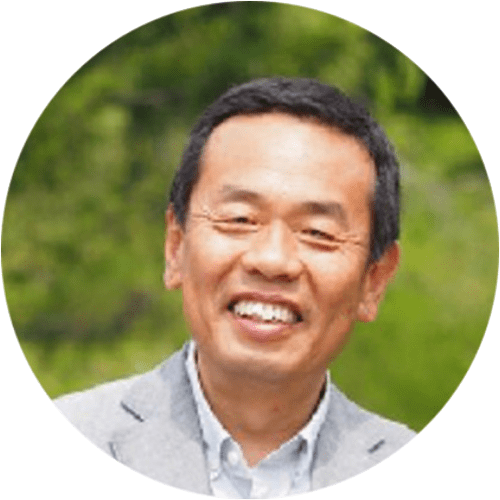
山梨県立大学/ 人間福祉学研究科 特任教授
大分大学/ 福祉健康学部 特任教授相澤 仁 教授
家庭養育優先の原則に基づき、すべての子どもが家庭の中で健幸な生活を営むためには、養育者をはじめ、子どもを取り巻く関係者が被包感のある温かな手を携えて和をつくり、子どもをパートナーとして尊重し、ともに生きていくことではないでしょうか。
そのため、養育者は「人に支援を求めることができること」「仲間と子どもの養育について共感し理解しあい、心を癒すとともに自身をエンパワメントすること」など人とつながり合い、ともに良好なコンディションで子どもを養育していくことが大切なのです。
手を携えて和をつくりましょう!! 私はこの活動を推進しています。里親の皆様、この活動に参加し、子どもとつくる健幸な未来を求めて交流してみませんか。 -

静岡大学 / 人文社会科学部 社会学科
白井 千晶 教授
社会の全員が里親になるのでも、社会の全員が里親に子どもをお願いするのでなくても、里親が多い社会、里親子が暮らしやすい社会は、子育てを助け合える社会、子どもが愛される場所がある社会、多様性が尊重される社会なのだろうと思います。誰もが暮らしやすい社会なんですね。
ですから、里親さんも、里親に関心がある人も、里親さんを支えたい人も、市民も企業も、チームで関わるOneLoveプロジェクトは、里親子のためだけでなく、私たちみんなの笑顔が増える社会を作ることにもつながると思います。ぜひあなたの関わり方で、参加して下さい。 -

福山市立大学 / 教育学部 児童教育学科
野口 啓示 教授
施設職員から里親になって感じたことは里親への支援の少なさです。
また、情報もなかなか入って来ません。そういう中、里親を支援することを目的とした里親コミュニティ&ポータルサイトの立ち上げにより救われる方がたくさんいると思います。 -
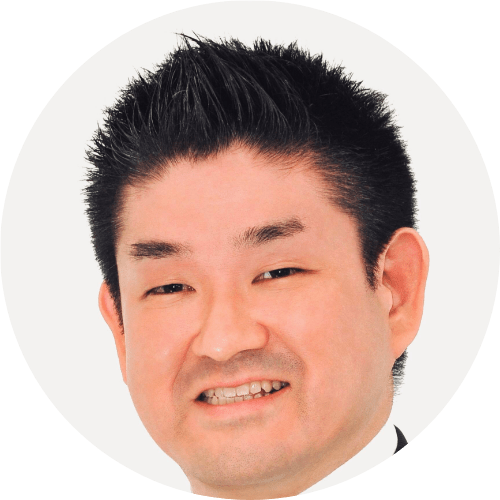
奈良市長
仲川 げん
奈良時代の高僧に良弁という方がいます。 一説に、幼子の時に鷲にさらわれ若狭から奈良までやってきたそうですが、義淵という僧侶に育てられ立派に成長。東大寺の創建に尽力したことから初代別当を務めるまでになります。
今でもその物語は市民劇団によって語り継がれ、100回以上の公演を重ねるに至ります。
1300年以上前の話ですので事実関係は定かではありませんが、実親の元を離れ子どもが生活するという事は今以上に当たり前だったのかも知れません。
昨今、社会的擁護の必要性が急速に社会の中心課題に挙げられるようになってきました。
多様な子育て、多様な家族の形を社会全体で暖かく包み込むような日本になるよう、日本こども支援協会さん、そしてONE LOVEサイトの活動に心より期待申し上げます。 -

大阪府子ども家庭サポーター
辻 由起子
『当たり前の日常を、当たり前に過ごすことができない。普通の暮らしが難しい。』
そんな親子が今沢山いて、様々な課題を抱えて悩んでいます。知ってしまったからには、見て見ぬふりはできません。
私たち一人ひとりにできること。「里親」という制度を使って「暮らし」や「子育て」を支えるお手伝いをすることができます。
全ての子どもがぬくもりにあふれた当たり前の日常を過ごせるように、まずは里親について知ってください。
社会で起きている問題はすべて、社会の一員である自分につながっている問題なので、一人ひとりの優しさを持ち寄り、ぬくもりの連鎖を広げていきたいです。 ONE LOVE。みんな一緒に。 -

株式会社ママの夢 代表取締役
株式会社マザープラス 代表取締役巽 房子
里親というと特別なことと思われがちですが、社会全体で子どもたちを育てるというのは誰もが理想とすることだと思います。
私自身、子どもが大好きなので、虐待や貧困など、子どもを取り巻く環境の厳しさを伝えるニュースが増えている中、「どうにかしてあげたい」と歯痒い気持ちでいっぱいです。
海外などではよく聞きますが、まだまだ日本では里親制度は一般的ではなく、聞いたことはあっても細かいところは知らない方が多いのではないでしょうか。このサイトでは、この里親制度を身近に感じてもらい、私たち自身が何ができるかのヒントを得られるのではないかと思います。
未来を担う子どもたちみんなが笑顔になる社会を一緒に作っていきましょう。 -

NPO法人バディチーム 代表
岡田 妙子
全国の里親さん達が自宅に居ながらにして繋がれる!
オンライン里親会には、これまでは考えられなかった新しい時代の最前線の取り組みとして敬意を表しつつ、果てしない可能性を感じています。
里親さんには同じ里親さん同士の支え合いが何より大切と言われている中で日頃の地域の仲間とはまた違った里親さん同士の繋がりの場があるということはとても意義深いと思います。
私達バディチームもNPOとして一般市民が里親さんの家庭に伺い育児・家事のお手伝いをするという活動を行っていますが里親さん達に何もかもお任せする社会ではなく、みんなで子育てができる社会になるよう「オンライン里親会」との出会いの中で気持ちを新たにしているところです。 -

特別養子縁組/養育里親 ・ あゆみの会 代表
志賀 志穂
全国の特別養子縁組や里親、ステップファミリーなど血縁によらないご家族をつなぐ「あゆみの会」の代表をしております。里親を希望される方に「どんな人が良い里親なのか?」とよく質問されます。私の答えは「質問して下さったあなたのようにご自身の育児に過剰な自信を持ちすぎない里親。『子どもにとっての』ベストな選択や、答えの出ない子ども達からの真剣な問いを子どもと一緒にずっと悩み続けられる里親」。ONE LOVE オンライン里親会には沢山の仲間がいます!私達と共に泣いて笑って愛しさもしんどさも分かち合える里親仲間をお待ちしております。
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える














