© ONE LOVE All Rights reserved.
- HOME
- 里親セミナーレポート
- 里親等委託の推進について
里親等委託の推進について
今回の講演者
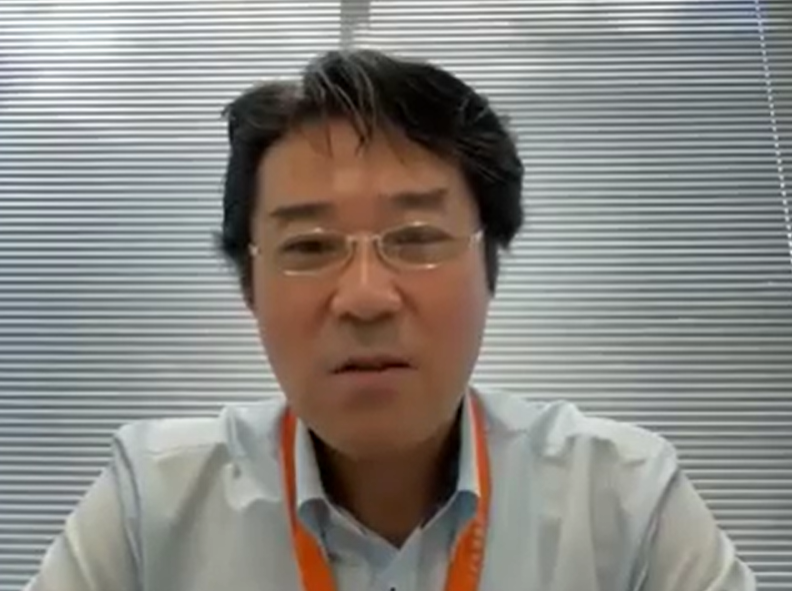
小松 秀夫 氏
こども家庭庁支援局家庭福祉課
第30回の里親セミナーでは、こども家庭庁支援局家庭福祉課 小松秀夫氏をお迎えし、国として里親委託の推進をどのように進めているかご講演頂きました。
講演内容① 社会的養護の全体像
実親支援と代替養育環境の重要性:地域に根ざした養育支援のあり方
1. 実親養育の重要性:
行政では、「子どもはできる限り実の親のもとで育つのが一番良い」という考え方を基本としています。そのため、市区町村が中心となって、実親が子どもを育て続けられるように様々な支援を行うことが重要だとされています。この支援によって、実親が安定して継続的に子どもを養育できることを目指しています。
2. 実親養育が困難な場合の対応:
しかし、どうしても実親のもとで生活できない子どもたちもいます。そうした子どもたちには、実親に代わる「家庭と同じような環境」を提供する必要があります。具体的には、養子縁組、里親、ファミリーホームといった方法を通じて、家庭的な環境での養育を目指します。
3. 施設入所という選択肢:
一方で、子どもが実親以外の家庭に入ることに抵抗を感じる場合や、特別な支援が必要な場合には、児童養護施設などの施設に入所することも選択肢の一つとなります。
4. 施設における家庭的環境の提供:
施設で生活する場合でも、子どもたちに「できる限り家庭に近い環境」を提供することが大切です。そのため、大規模な施設ではなく、小規模で地域に分散された施設での生活が推奨されています。
5. 地域小規模児童養護施設(グループホーム)の例:
例として、小松氏は、空き家となった一般の住宅を利用して、4〜6人の子どもたちが一緒に生活する「地域小規模児童養護施設(グループホーム)」の運営を紹介しました。これは、より家庭的な雰囲気の中で子どもたちが生活できるようにするための取り組みです。

社会的養護の現状と課題:児童虐待対応と支援体制の強化の必要性
令和3年度のデータによると、児童相談所が対応した児童虐待相談件数は20万件を超え、そのうち約13%で親子が一時的に離れて保護されています。最終的には約2%の子どもたちが施設や里親のもとで生活を送ることになります。
現在、約4万2千人の子どもたちが里親家庭やファミリーホーム、または乳児院や児童養護施設で暮らしており、虐待対応件数の中から約4,400人が里親や施設に措置されていると小松氏は説明しました。これは、多くの子どもたちが家庭環境で育つことができず、代替的な養育環境を必要としていることを示しています。
児童養護施設や里親制度の受け入れ枠には限りがあり、全ての子どもたちを支援することが難しい状況です。
里親制度の認知度が低く、里親の数が不足しているため、多くの子どもたちが施設での生活を余儀なくされています。
施設や里親家庭で育った子どもたちが成人し、社会に出た後の支援が十分ではありません。自立に向けた継続的なサポートが求められています。
また、児童虐待の未然防止や兆候の早期発見・介入のため、地域社会との連携や相談窓口の充実が重要です。
このように社会的養護の現状は非常に厳しいものであり、多くの子どもたちが適切なケアを受けるための制度や支援体制の強化が求められているのです。
里親制度から虐待対策までの多面的な改善の必要性
全国的に登録里親の数は増加しているものの、実際に子どもが委託される割合は低く、制度やファミリーホームの活用促進が課題です。
里親等委託率は国際水準と比較して依然として低く、制度の強化が求められています。地域ごとの委託率の差を分析し、成功事例を参考に全国的な改善が必要です。各自治体が委託率のデータを効果的に活用し、改善に向けた具体的な取り組みを進めることが重要です。
乳児院や児童養護施設は、家庭での養育が難しい子どもたちを支援する重要な役割を果たしていますが、より家庭的な環境の提供が求められています。また、特別なケアを必要とする子どもたちへの支援体制が十分ではないことも課題です。
さらに、虐待経験を持つ子どもの増加は深刻な問題であり、特に里親家庭での虐待が顕著です。心理的虐待(面前DVを含む)も増加傾向にあります。発達障害やPTSDを抱える子どもも増加しており、特別な支援が必要です。
このように社会的養護には多くの課題が存在し、里親制度の推進から虐待対策、施設環境の改善、社会復帰支援の充実まで、各分野での改善が急務です。
特に、里親制度の活用促進、施設における家庭的環境の提供、虐待経験を持つ子どもへの専門的なケアの提供、そして社会復帰後の自立支援の強化が重要となります。

講演内容② 各自治体の社会的養育推進計画
次期社会的養育推進計画:家庭養育優先とケースマネジメント強化への道
次期社会的養育推進計画は、子ども家庭庁が各自治体に対し、社会的養護の推進に関する具体的な計画を作るように求めるものです。この計画には、児童相談所や市町村の体制強化、里親・ファミリーホームへの支援、児童入所施設の小規模化・多機能化などが含まれます。この計画は、平成28年に改正された児童福祉法に基づく新しい社会的養育ビジョンに基づいており、各自治体の積極的な取り組みが求められています。
この計画の中心となる理念は、「家庭養育優先原則」と「パーマネンシー保障」の2つです。
- 家庭養育優先原則: 子どもはできる限り実親のもとで育つことを最優先とする方針です。そのため、家庭への支援を強化します。
- パーマネンシー保障: 代替養育が必要な場合には、子どもが安定した環境で継続的に養育を受けられるようにすることを意味します。具体的には、親族里親、養育里親、ファミリーホームなど、子どもの状況に合った最適な養育先を選定します。
さらに、代替養育が必要な子どもたちにはケースマネジメントが非常に重要です。
家庭養育優先原則とパーマネンシー保障に基づき、子どもが最適な環境で育つためには継続的な支援が欠かせません。そのため、児童相談所の体制整備、具体的にはケースマネジメントを担当する専門チームや担当係の配置が推奨されています。
子育て短期支援事業:市区町村主体の支援
「子育て短期支援事業」は、市区町村が中心となって行う事業で、里親、ファミリーホーム、児童家庭支援センターなどを活用して、ショートステイなどの支援を提供します。これらの資源を効果的に活用するため、自治体には情報提供や名簿作成などの支援が求められています。
里親支援センター:里親支援の拠点
里親支援センターは、里親を支援するための重要な施設です。里親のリクルート(募集)、トレーニング(研修)、子どもとのマッチング、日常的なサポートなどを行います。里親等の委託率を向上させるためには、このセンターが各自治体で適切に機能することが重要です。
乳幼児期の委託:愛着形成を重視
特に乳幼児期の委託においては、子どもの愛着形成の観点から、養子縁組や里親、ファミリーホームへの委託が原則とされています。乳児院に長期入所している子どもたちについては、できるだけ早く里親等への委託に切り替えることが求められており、この取り組みが国の目標である委託率の向上に貢献すると考えられています。
国の目標:委託率の引き上げ
国は令和11年度までに、乳幼児の里親等委託率を75%以上、学童期以降の委託率を50%以上に引き上げるという目標を設定しています。各自治体には、これらの目標を達成するために具体的な計画を策定し、体制整備を進めることが求められています。
計画の成功の鍵:自治体の実施と体制強化
社会的養育推進計画の成功には、各自治体が計画を実行することが不可欠です。
特に、里親支援センターの設立やケースマネジメントの強化が鍵となり、これらが今後の計画策定と実施において効果的に機能することが期待されていると小松氏は話しました。
講演内容③ 里親委託の推進施策
里親委託推進施策の展開:新指標導入と全国的な支援体制の強化
国は里親委託を推進するため、令和6年度から新たな通知を発出し、現状の委託状況を分析しました。この分析に基づき、今後の取り組みが整理され、改善策が進められています。
現状の委託率と国の目標
現在の里親等委託率は23.5%です。これは、乳児院、児童養護施設、里親ファミリーホームに入所している子どものうち、里親やファミリーホームに委託されている子どもの割合を示しています。
国は、3歳未満の子どもの委託率を75%、学童期以降の子どもの委託率を50%に引き上げることを目標としており、これが達成されると全体の委託率は56.2%に達する見込みです。
新指標:「登録率」と「稼働率」
里親等委託の状況を評価するために、新たに「登録率」と「稼働率」という指標が導入されました。
- 登録率: 代替養育が必要な子どもに対して、どれだけの受け皿(里親やファミリーホーム)が用意されているかを示します。
- 稼働率: 用意された受け皿に、実際にどれだけの子どもが預けられているかを示します。
国の目標達成に向けた基準として、登録率56.2%が設定されています。福岡市や新潟市など、目標を達成している自治体もありますが、すべての里親やファミリーホームが常に満杯(100%稼働)という状態は現実的に難しいとされています。
自治体の分類と改善策
自治体は、里親等委託率と登録率の進捗状況に応じて4つのグループに分類され、それぞれの特徴と課題に基づいた改善策が進められています。
- 委託率・登録率ともに順調な自治体: 特に課題がない、または少ない状態。
- 委託率は伸びているが、登録率が低い自治体: 里親の数は足りているが、子どもを預けるに至っていないケースが多い。マッチングや支援体制に課題がある可能性。
- 登録率は高いが、委託率が伸びていない自治体: 里親の登録はあるものの、実際に子どもを預かるに至っていないケースが多い。里親側の事情や、子どもとのマッチングに課題がある可能性。
- 委託率・登録率ともに伸びていない自治体: 里親の確保と、子どもを預かる仕組みの両方に課題がある状態。
全国的な課題と取り組み
里親等委託を全国的に推進するためには、以下の課題が特に重要です。
- 登録里親の確保: 里親になる人を増やすこと。
- 養育技術・経験のばらつき: 里親の養育スキルに差があること。研修などで質の向上を図る必要性。
- 子どもとのマッチング・里親家庭の継続的な支援: 子どもと里親の相性を見極めること、委託後の継続的なサポートが重要。
- 実親の同意の取得: 里親委託には原則として実親の同意が必要であり、その手続きが課題となる場合がある。
各課題に対応するため、国全体で以下の取り組みが進められています。
- ・社会的養育推進計画の見直し
- ・里親支援センターの創設と人材育成
- ・里親への委託前の養育支援事業
- ・ファミリーホームの機能強化
これらの施策は、里親やファミリーホームの支援体制を強化し、里親等委託の推進を加速させることを目的としています。

行政は里親委託の推進に向けて、制度の改正や支援体制の強化など、様々な施策を行っていることが分かります。
令和6年4月には、「児童自立生活援助事業」が施行されました。これにより、支援を受ける子どもの年齢に関わらず、支援を継続することが可能になりました。特に自立が難しい子どもたちに対して、個々の状況に合わせた柔軟な支援を提供できるようになりました。
これまでは支援を受けられる年齢に上限があったり、市町村によって支援の内容にばらつきがあるなどの課題がありました。しかし、国が都道府県を支援する体制を作り、年齢に関わらず支援を続けられる制度ができたことによって、より多くの子どもたちが、より長く、より質の高い支援を受けられるようになることが期待されます。
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える














