© ONE LOVE All Rights reserved.
- HOME
- 里親セミナーレポート
- こどもと里親の「はじまり」からの支援
こどもと里親の「はじまり」からの支援
今回の講演者
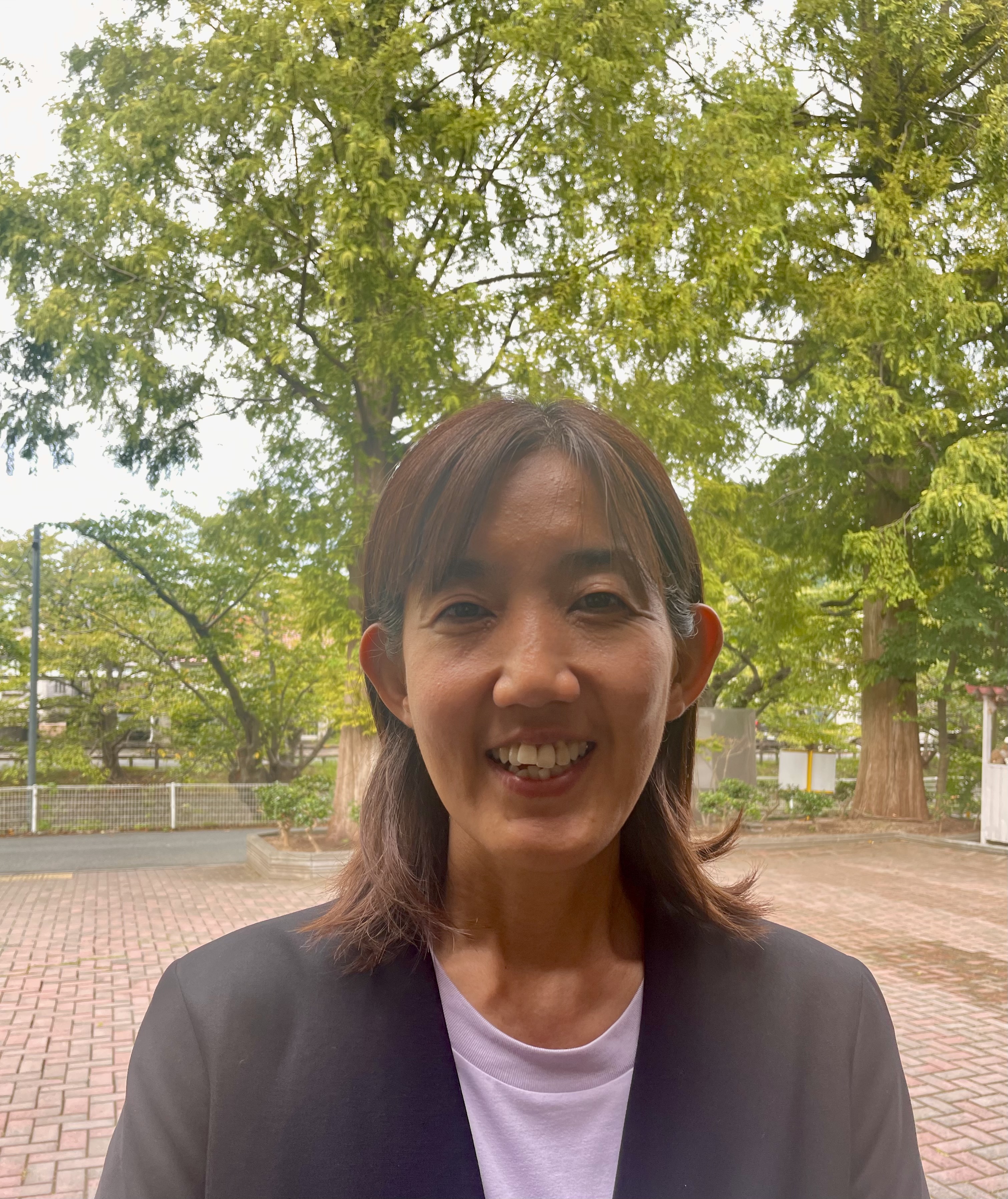
清水 暁子氏
里親家庭サポートセンターいろはセンター長
今回は、里親家庭サポートセンターいろは センター長の清水暁子氏に「こどもと里親の『はじまり』からの支援~里親センターの現状報告と可能性~」というテーマで講演いただきました。
目次
清水暁子氏は明治学院大学大学院を卒業後、社会福祉士の資格を取得。
6年間の児童クラブ指導員勤務やキャンプ活動を通じ、子どもたちと長く関わってこられました。その後、ご家族とともに移り住んだ鳥取県で鳥取子ども学園に勤務。故・藤野光一氏(同学園元会長)の助言で里親支援の道を選ばれました。以降12年間里親支援専門相談員として活動し、現在は「里親支援センター いろは」のセンター長を務めています。
講演内容① 里親支援センター「いろは」設立と鳥取県の里親事情
鳥取県の里親支援センター「いろは」は、令和6年4月に新たに設立されました。鳥取こども学園の施設の一つであり、現在は清水氏を含めて5名の職員が在籍しています。里親の啓発、里親募集や登録の支援、各種研修の提供、里親と子どもとのマッチング、里親家庭の養育のサポート、子どもの自立サポートなどを包括的に担っています(=フォスタリング体制)。センター名の「いろは」は、ものごとの始まりを意味することから、里親と子どもが出会い共に歩み、サポートするための場でありたいという願いが込められていると清水氏は語りました。
「いろは」のある鳥取こども学園は、1906年に鳥取孤児院として設立され、現在では14の施設・事業所を運営しています。敷地内には、「いろは」のほかにも図書館や体育館、子育て支援センターや児童家庭支援センターなどが併設され、1つの大きなコミュニティとなっています。清水氏は、地域の目につきやすい場所に設置することで「いろは」の職員が堂々と活動し、その重要性を学園内外に認識してもらうことを目指したとのことです。このことは清水氏の活力にもなっていると語ります。
清水氏は続けて、鳥取県の里親支援状況について語りました。
鳥取県は東部、中部、西部の3つの地域に分かれており、各地域に児童相談所や里親会、児童養護施設やファミリーホームがあります。「いろは」を含む鳥取こども学園は東部を拠点に県全域で支援活動を行っています。
鳥取県の里親の数は平成24年度から現在まで1.8倍と増加傾向です。令和2年度から養子縁組里親と養育里親の重複登録が可能になったことも増加の一因です。約3割の養育里親が長期的な養育に備えているとの調査結果がありますが、子どもの選択肢を増やすため、里親数はさらなる増加が求められます。
また、里親家庭の数は東部よりも西部(米子地域)で多いことから、西部への支援センターの機能拡充が課題であるといいます。
平成24年度から令和6年度にかけて、鳥取県の里親委託率は1.5倍に増加し、委託検討件数も全体としては増えつつあります。しかし最近では横ばいもしくはやや減少傾向で、国や県の目標値には届かないのが現状です。清水氏は委託件数の重要性の一方、里親のもとで生活を始めた子どもが安心して長く暮らせる支援が必要と述べます。里親との信頼関係を築くことで子どもの新しい生活をサポートすることが特に重要だと清水氏は語ります。
このような地域の実情と課題をふまえ、「いろは」の意義や背景として主に次の要素が挙げられました。
・従来の里親支援機関を強化・拡充:人員・設備の拡充、フォスタリング業務拡大
・鳥取こども学園から続く理念:制度の有無にかかわらず必要とされる支援を実行
・県東部地域における官民協働によるフォスタリング体制(包括的な支援体制)が可能になってきたこと
清水氏は「いろは」の支援業務を、里親の意見を取り入れた新たな里親支援のかたちとして発展させたいと考えています。

講演内容② 里親支援の課題と取り組み
里親支援とは、子どもが里親を必要とした瞬間=「はじまり」から、里親や関係機関の職員が多くの決断を重ね、支援を行うことです。単に子どもが施設から里親のもとへ移ることをゴールとせず、その後も課題をともに解決していくものと清水氏は語ります。里親支援センターの取り組みの基盤となるのはこうしたその時々で最善の支援方法=「ベストプラクティス」の積み重ねだと清水氏は捉えています。
ここで清水氏は6人の子どもの事例を挙げました。各事例について、施設入所時期、入所にいたる背景、里親委託までの経緯、その後の継続支援などが詳しく語られました。
清水氏がなかでも重要な出会いとして最初に挙げたのは、適切な支援や信頼関係の構築ができず、里親委託後に再び児童相談所の支援が必要となった子の事例でした。里親委託が難航し4歳まで委託が決まらなかったこと、子どもと愛着を持つ担当職員との関係を引き渡し時に断ってしまうという当時の問題点や、里親への支援の不十分さなど、マッチング方法や支援体制における課題を痛感したといいます。
以降の事例では、
・里親と子どもの信頼関係を築くことにつなげるために、責任をもって計画・支援体制を整えることの重要性
・子どもと里親の関係は「運命の出会い」だけで成り立つものではなく、適切な支援によって育まれること
・実親の希望を尊重しつつ、子どもが新たな家族で安心して成長できるような支援
・子ども・実親・里親と「共に歩む」姿勢の大切さ
・里親が協力しやすいかたちでの実親と子どもの面会支援
・実親・里親それぞれへの継続的な支援
・実親の関係が希薄、里親との関係が安定しない子に寄り添った継続的支援
というように、支援に際して重要だったポイントや具体的な支援が挙げられました。清水氏は、これらの事例から、里親支援センター等を拠点にしたフォスタリング体制の整備がやはり重要であると語りました。

講演内容③ 里親支援センターとしてのチャレンジと可能性
清水氏は今後のセンター運営において、
(1)里親のはじまりに寄り添うこと
(2)施設養育と里親養育の統合
(3)ソーシャルワーカーの人材育成
を挙げ、支援の質の向上を図ることが重要だと語りました。
里親委託は、単に親が育てられないからというだけでなく、子どもにとって親や家庭が必要であり、またそれが子どもや里親家庭の幸せにつながることから始まるものです。
そのため、(1)にあるように里親希望者のすそ野を広げ、「里親として生きる」選択を共にしたいと氏は考えています。
また、(2)については、施設の子どもや里親希望者と屋外で遊んだ自身の経験から、複合型の社会施設として子ども・里親・支援者が交流できるような一体型の支援拠点を作りたいと語りました。
(3)の人材育成において、個々の支援からのリアルな体験を通じ、必要な支援を敏感に捉え、行動に移せる職員を育てることの重要性を説きました。

清水氏は、こどもと里親の「はじまり」に関与することが、子どもや里親への長期的な支援に繋がり、また他の施設や家庭でも応用できると繰り返し述べ、今後も里親と子どもたちの「はじまり」からの支援にこだわり続け、里親支援センターとしての業務を推進していきたいという強い意志を表明し、感謝の言葉で講演を締めくくりました。
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える














