© ONE LOVE All Rights reserved.
デモンストレーションで学ぶプレイセラピー
今回の講演者
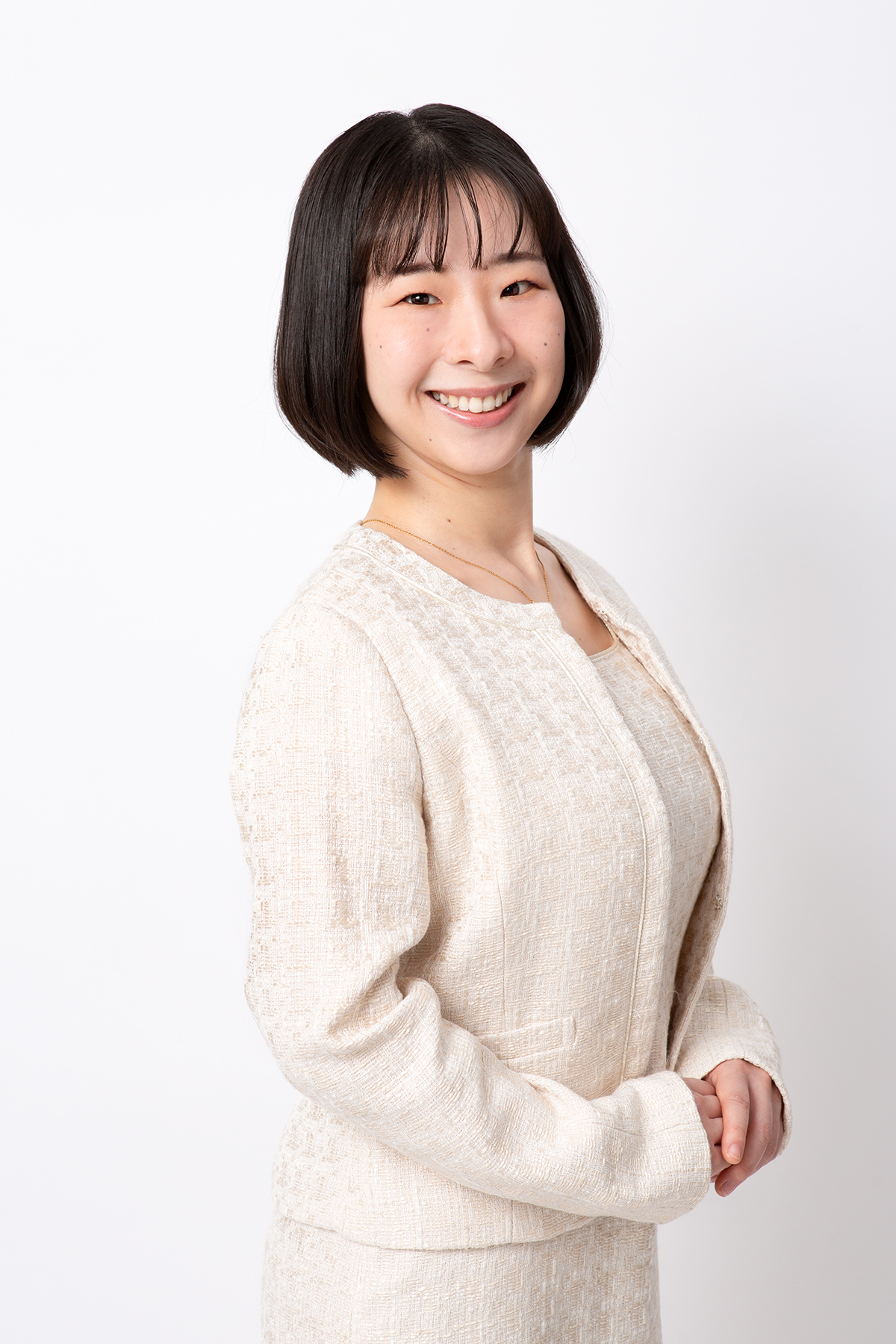
川島 梨瑛 (かわしま りえ)氏
ことのは心理療法オフィス
公認心理士・臨床心理士
臨床発達心理士・認定専門公認心理士
はじめに
今回は、里親家庭への心理支援で豊富な経験を持つ川島梨瑛 氏をお迎えして「里親家庭への心理支援」をテーマに講演していただきました。
川島氏は大学卒業後、都市の発達相談センター、放課後等デイサービス、児童相談所で心理判定員として勤務し、多くの里親家庭と関わってこられました。 精神分析的心理療法をオリエンテーションとしながら、目の前のクライエントに役立つ支援を軸に活動されています。現在は日本こども支援協会のオンラインサロンへの参加や毎週木曜21時からの個別相談を担当されています。
講演内容① 里親支援への関わりと現状の課題
日本こども支援協会との出会い
川島氏が里親支援に深く関わるようになったきっかけについて、印象深いエピソードを紹介されました。
コロナ前、児童相談所で虐待家庭を支援していた際、あるお子さんを里親家庭に委託したことがありました。その里親さんは複数の子どもを同時に受け入れておられ、とても大変な状況で頻繁に相談を受けました。この経験を通じて「里親さんは本当に大変な立場だ」と痛感したと川島氏は振り返られました。
里親家庭への心理支援の現状と課題
現在、施設養育から家庭養育(里親・小規模グループホーム)への移行が進む一方で、心理支援は圧倒的に不足している状況があります。川島氏は以下の課題を指摘されました:
判定員の負担過多:1人で30〜50件を抱えるため、1組の里親さんに毎週面接することは現実的に困難
継続的支援の限界:制度上の制約により、十分な個別支援が提供できない
専門的支援の不足:里親家庭特有の課題に対応できる専門家が少ない
新たな支援モデルの模索
川島氏は子どもの心理療法のトレーニングで実施していた家庭訪問やグループスーパービジョンの経験から、「これは里親家庭にも応用できるかもしれない」と感じたそうです。
そんな時に日本こども支援協会の活動を知り、自ら連絡を取って現在の支援活動が始まりました。この経験から、既存の制度の枠を超えた新しい里親支援のあり方の重要性を強調されました。

講演内容② 発達障害と愛着障害の理解
川島氏は、里親家庭で多く見られる発達障害と愛着障害について、基礎的な理解を深めるための説明をされました。
発達障害の5つの分類
発達障害は大きく以下の5つに分類されます:
- 自閉スペクトラム症(ASD)
こだわりが強い
対人コミュニケーションが苦手
集団行動が難しい - 注意欠如多動症(ADHD)
落ち着きがない
不注意が目立つ
危険行動が多い - 学習障害(LD)
読字・書字・算数など特定領域のみ顕著に苦手 - 協調運動障害(DCD)
走ると手足が同時に出る
転びやすい
蝶結びや箸の使用が苦手 - 知的障害
IQ70前後以下で日常生活に広い困難
重要なポイントとして、川島氏は「各障害は重複しやすく、『どの傾向が強いか』を見ることが大切」と強調されました。
愛着障害(アタッチメント)の4類型
ボウルビィの古典的4類型について説明されました
- 安定型
親を適切に頼り、安心すると再び探索に戻れる - 葛藤型(抵抗/両価型)
近づきたいがイライラも強く、泣き叫びが長引く - 回避型
親を頼れず一人で我慢してしまう - 無秩序型
親の対応が一貫せず、子どもは凍りつきやすい 川島氏は「里親家庭では無秩序型が目立つ印象がある」と臨床経験を基にした見解を示されました。

講座内容③架空事例を通じた実践的アプローチ
川島氏は2つの架空事例を通じて、実際の個別相談でのアプローチ方法を具体的に紹介されました。
事例1:Aさん(小学5年生・女子)
背景:
ネグレクト家庭で育ち、小学1年生で里親委託
児童相談所でASD、ADHD、愛着障害と診断
学校では大人しく問題なしだが、家庭では里母にのみ暴言・暴力
里父には懐いている、こだわりが強く切り替えが苦手
個別相談でのアプローチ:
具体的エピソードの詳細な聞き取り:
「あと○分で終わろう」「19時に夕飯」等の視覚的スケジュールを提案
里親さんの思いを丁寧に聴取:
里親になった動機、子どもに望む成長像を聞き、励ましと肯定を実施
背景要因の共有:
実親との比較やこれまでの養育歴が行動に影響している可能性を一緒に考える
柔軟性の提案:
里親さんのルールや価値観は尊重しつつ、伝え方や双方が歩み寄る方法を提案
事例2:Bくん(小学2年生・男子)
0歳で入所、3歳で養育里親に委託
実母との月1回面会が継続
面会後は必ず里親家庭で激しい癇癪
食事・入浴・就寝が困難になる
個別相談でのポイント
子どもの気持ちの言語化:実母と里親の間で揺れる子どもの気持ちを言語化し、里親と共有
里親自身の感情への配慮:
里親自身の実母への複雑な感情も扱い、「親が疲れないこと」を強調
具体的なリフレッシュ方法:
平日昼の夫婦散歩、週末の親子公園遊びなど具体的な方法を提案
チーム支援の重要性:児童相談所への相談しづらさに共感しつつ、チームとして積極的に頼ることを提案
心理支援の基本姿勢
川島氏は、心理支援について重要な原則を示されました
「心理支援は『一緒に考える場』であり、指示・評価の場ではない」
この姿勢が、里親さんとの信頼関係構築と効果的な支援につながることを強調されました。
支援者としての気づき
川島氏は、日本こども支援協会での個別相談を通じて感じた率直な思いを共有してくださいました。
「自分の無力感を感じることもありました。里親さんはすでに全力で頑張っておられ、私にできるのは話を聴くことくらい。しかし『話を聴いてもらえただけでホッとした』と言っていただけることに、私自身が支えられています」
また、「制度面の理解はまだ勉強中ですが、里親さんの真摯さに触れ、こちらが力をもらう場面も多い」と述べ、支援関係の相互性についても言及されました。
この講演を通じて、里親家庭への心理支援の現状と課題、具体的な支援方法について深く学ぶことができました。 特に、発達障害と愛着障害の基礎理解から実践的なアプローチまで、幅広い内容が提供され、里親支援の質向上に向けた貴重な知見が共有されました。
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える














