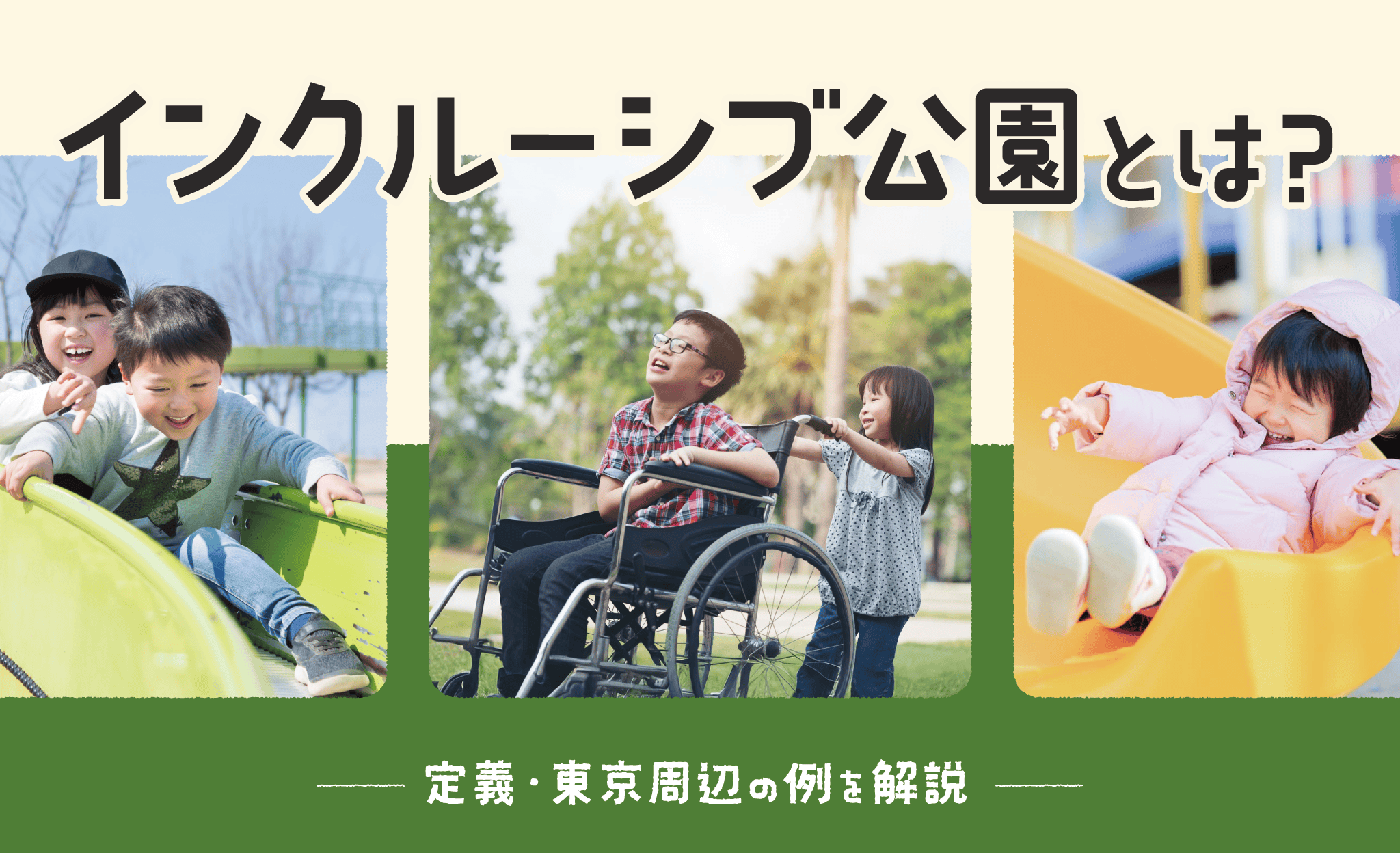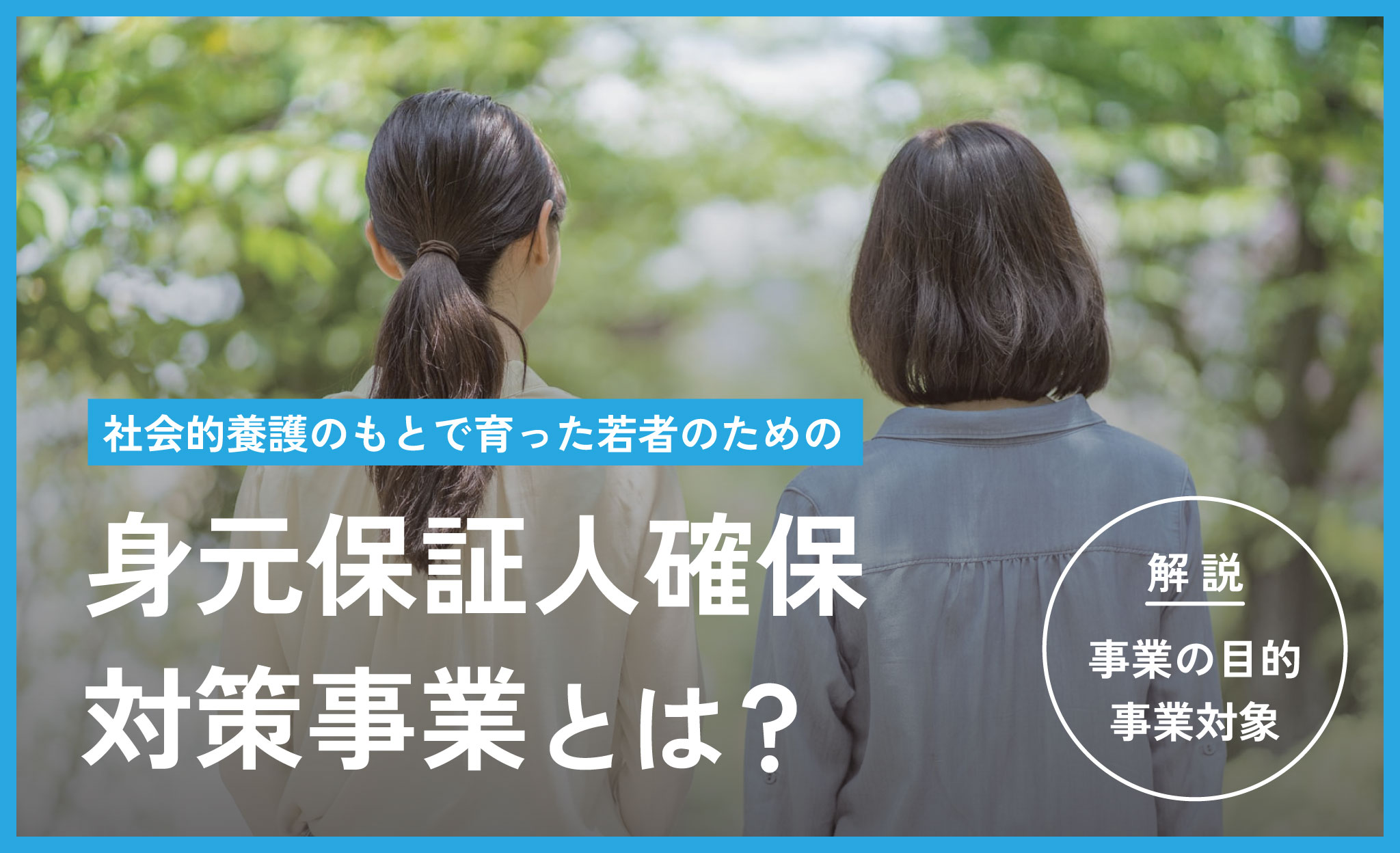自立
知的・発達障害を持つ人のためのセルフアドボカシーとは?言葉の意味を解説

まだあまり多くはないかもしれません。
近頃よく目にする「合理的配慮」や「障害者差別解消法」について考える時、
このセルフアドボカシーという言葉が非常に重要になります。
この記事では、セルフアドボカシーの意味や、なぜそれが重要であるかについてご紹介します。

セルフアドボカシーとは
セルフアドボカシー(英語:Self-Advocacy)とは、
日本語で「自己権利擁護」と訳され、
障害がある方や何らかの困難に直面している人が、
自分自身のために立ち上がり、自分の希望や権利、
必要とすることを自分の言葉でしっかりと伝えることです。
セルフアドボカシーの考え方は、
自分自身の人生について主体的に決めていく大切さを教えてくれます。
重要性
障害を持つ人々は、歴史的に「助けを受ける側」とみなされ、
自分のことは他人が決めるものとして、
自分の意見を言う機会が少ないという状況がありました。
これは、障害者の人たちが自分で自分の人生について
決める権利を十分に持っていないとも言える状態です。
例えば、知的障害がある人が自分に関する決定をする際、
その人の判断能力が問題視されることがあり、
結果として他の人がその人にとって最良だと思われる選択を代わりにすることもあります。
このような状況は、その人が自分の意見を表明したり、
自分の選択をする機会を失ったりすることを意味しています。
言うまでもなく、私たちの仕事や生活のスタイル、
お金の使い方、幸せの形は、誰かが勝手に決めるものではありません。
自分で考え、声を上げ、選択する権利があります。
これは、障害がある人もない人も同じです。
世界中で障害者の権利を守るための条約が結ばれ、
障害を持つ人々の「自己主張(セルフアドボカシー)」について、
改めて考える動きが広がっています。
セルフアドボカシーの考えが広まることで、
障害を持つ人たちが、これまでのようにただ助けを受けるだけの受動的な存在ではなく、
積極的に支援を求めて行動する主体的な存在として見られるようになるでしょう

子どものセルフアドボカシーを支援する仕組み
子どもの権利であるセルフアドボカシーを支援する取り組みとして、
各都道府県のガイドラインにより支援の仕組みも作られています。
「制度的アドボカシー」「非制度的アドボカシー」、
「ピアアドボカシー」「独立(専門)アドボカシー」
という4種類のアドボカシーの仕組みが確保され、
子どもがそれらの中からいつでも必要な支援を利用できる環境整備が、
各都道府県により推進されています。
自立に向けてセルフアドボカシーのスキルを育てることが大切
発達障害のある子どもたちは、
しばしば自分の思いを相手にうまく伝えるのが難しいと感じます。
障害が目に見えにくいため、
周りの人たちも彼らが何を求めているのかを理解するのが難しいこともあるでしょう。
こうした状況において、大人は良かれと思って子どもの代わりに話をすることが多いですが、
これが続くと、子ども自身の願いが見失われたり、
自分で意見を言う機会を奪ってしまったりするかもしれません。
ただ安全な道を用意するだけでは、
子どもたちが自分で歩いていく力は育ちません。
彼らが自分で周りの人たちと話し合い、
自分の意見を伝える力を育てるような支援を心掛けましょう。

ガイドブックをシェアする
自立の関連記事
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える