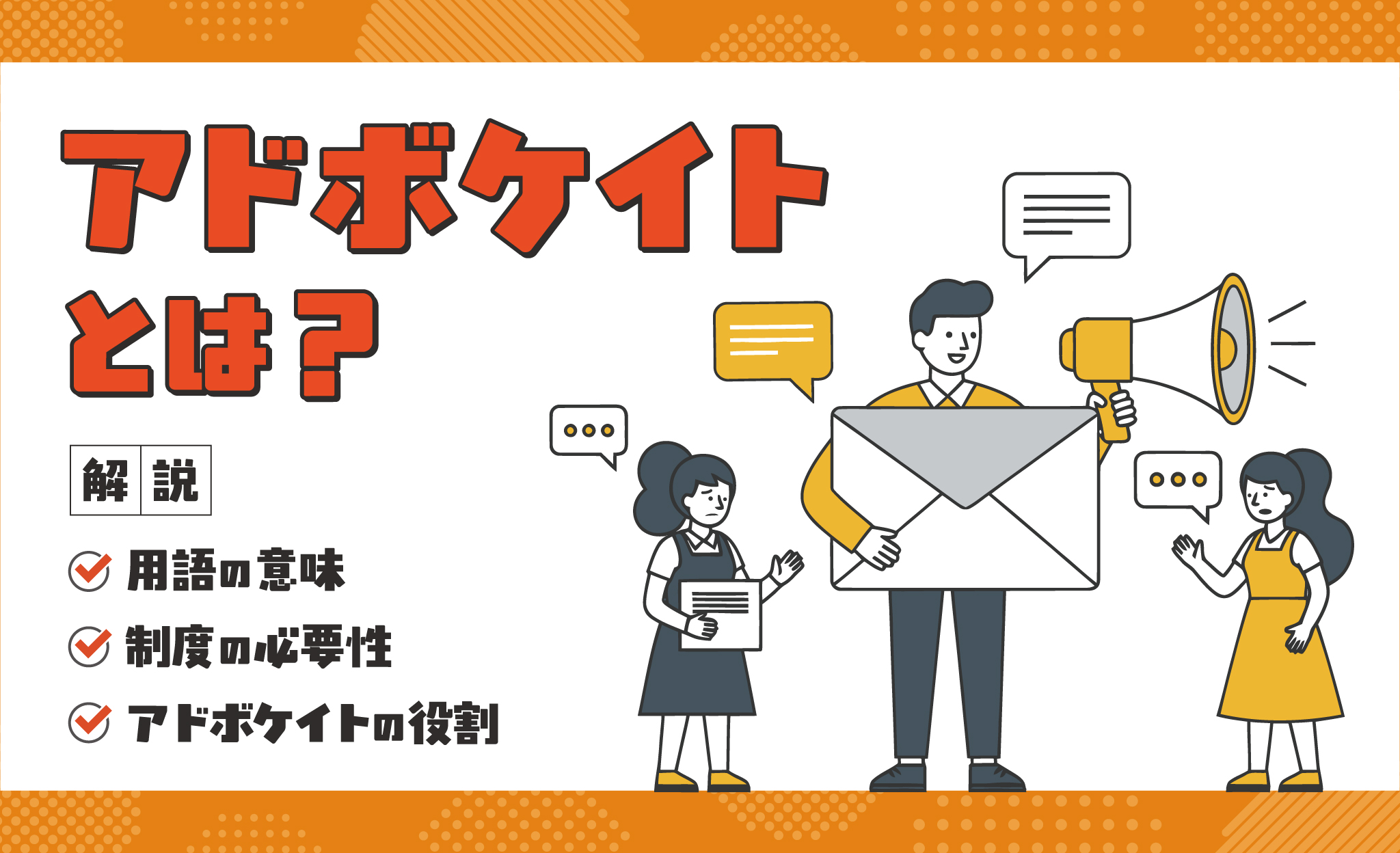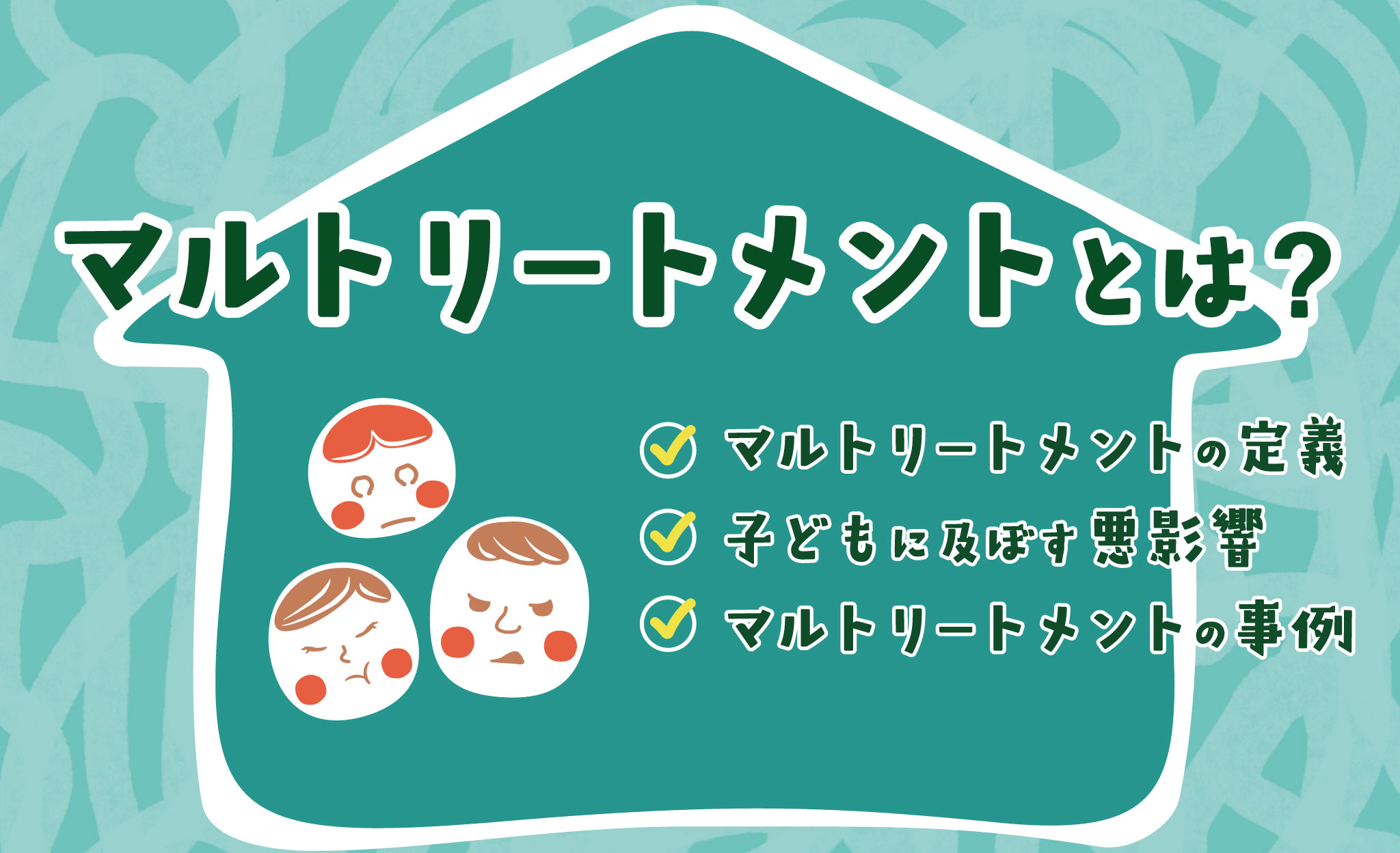子どもの社会問題
放置子とは?増加の要因と対応方法を解説
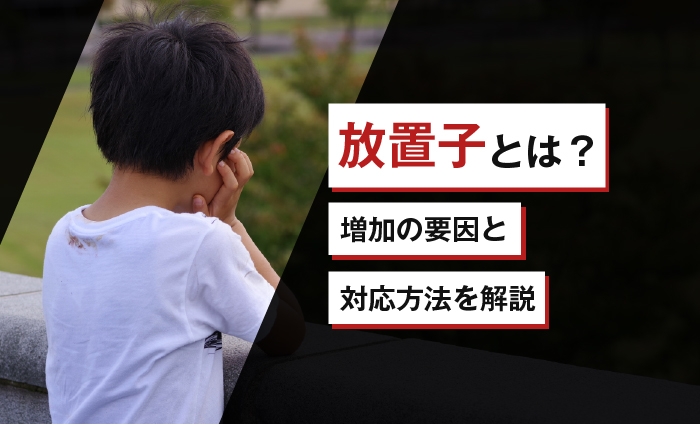
「見知らぬ子どもが家に勝手に入り込む」「見知らぬ子どもにおやつを要求される」。近年、無邪気や同情という言葉では片付けられない子ども「放置子」の存在がクローズアップされています。放置子への対応に悩みを抱えている人々の声が大きくなりつつあるのです。
そこで今回は、近年関心が高まっている放置子の問題について、概要や発生する要因、対応方法などをまとめました。
放置子とは
放置子とは、親から放ったらかしにされている(ネグレクトを受けている)子どもをさします。近所を歩き回ったり、顔見知りになった人の家に上がっておやつをねだったり、その家に居座って帰らなかったりするのが特徴です。
なお、放置子という名称については、2022年3月時点において福祉などの専門用語という位置付けにはなく、主にインターネット上で使用されている俗称です。
放置子の特徴的な行動例
-
放置子に見られる特徴的な行動の具体例を以下にまとめました。
- ●子どもよりも大人への関心が強く、大人に抱っこをせがんだり、
子ども同士で遊ぶよりも大人と過ごすことを優先したりする - ●断ったり拒否したりしても、なかなか諦めない
- ●友達である子どもの家に長居したがる
- ●早朝や夕方など、時間帯を問わず一人で外にいることが多い
上記の特徴に該当するならば、その子どもは放置子である可能性が高いです。
放置子のこうした行動を受けて、「毎日のように放置子が家に遊びに来て困っている」「いつまでも長居されるから、家事や食事などを行う時間が遅くなってしまう」などと悩んでいる方は少なくありません。
- ●子どもよりも大人への関心が強く、大人に抱っこをせがんだり、

放置子が増加する要因
放置子の存在が目立っている要因には、子供を育てる家庭環境の変化があります。もともと日本では専業主婦家庭が全体の多くを占めていましたが、現在では共働き家庭が多数派となっているうえに、ひとり親家庭も急増しており、子どもが親の存在なしで過ごさなければならない時間が増えています。
こうした環境の変化と放置子の増加には、少なからず関係性があると考えられています。
放置子への対応方法
放置子の行動に悩まされている場合、以下のような対応を取ることが望ましいです。
- ●学校に相談する
- ●自分の子どもと放置子を遊ばせる際に「決まり」を作る(時間帯、頻度など)
- ●毅然とした態度で接する
- ●虐待が疑われるならば、児童相談所に相談する
厚生労働省の資料によると、2020年度における児童相談所での虐待相談件数は205,044件であり、過去最多を記録しています。このうち、ネグレクトは、31,430件(15.3%)です。
特にインターネット上では放置子を「迷惑で邪魔な存在」と扱う人も見られますが、虐待を受けている児童の可能性もあることから、保護すべき対象として受け止め、必要に応じて児童相談所に相談することが大切です。
なお、児童相談所への相談は、匿名で行うことが望ましいです。なぜなら、相談時に自身の名前を明かしてしまうと、自身が通報した事実を放置子の保護者に知られてしまう可能性があるためです。児童相談所へ相談する際は、「疑わしい」と感じた点をしっかり伝えることで、匿名であっても緊急度が高いと判断してもらえます。
参考:厚生労働省「令和3年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料」
ガイドブックをシェアする
子どもの社会問題の関連記事
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える