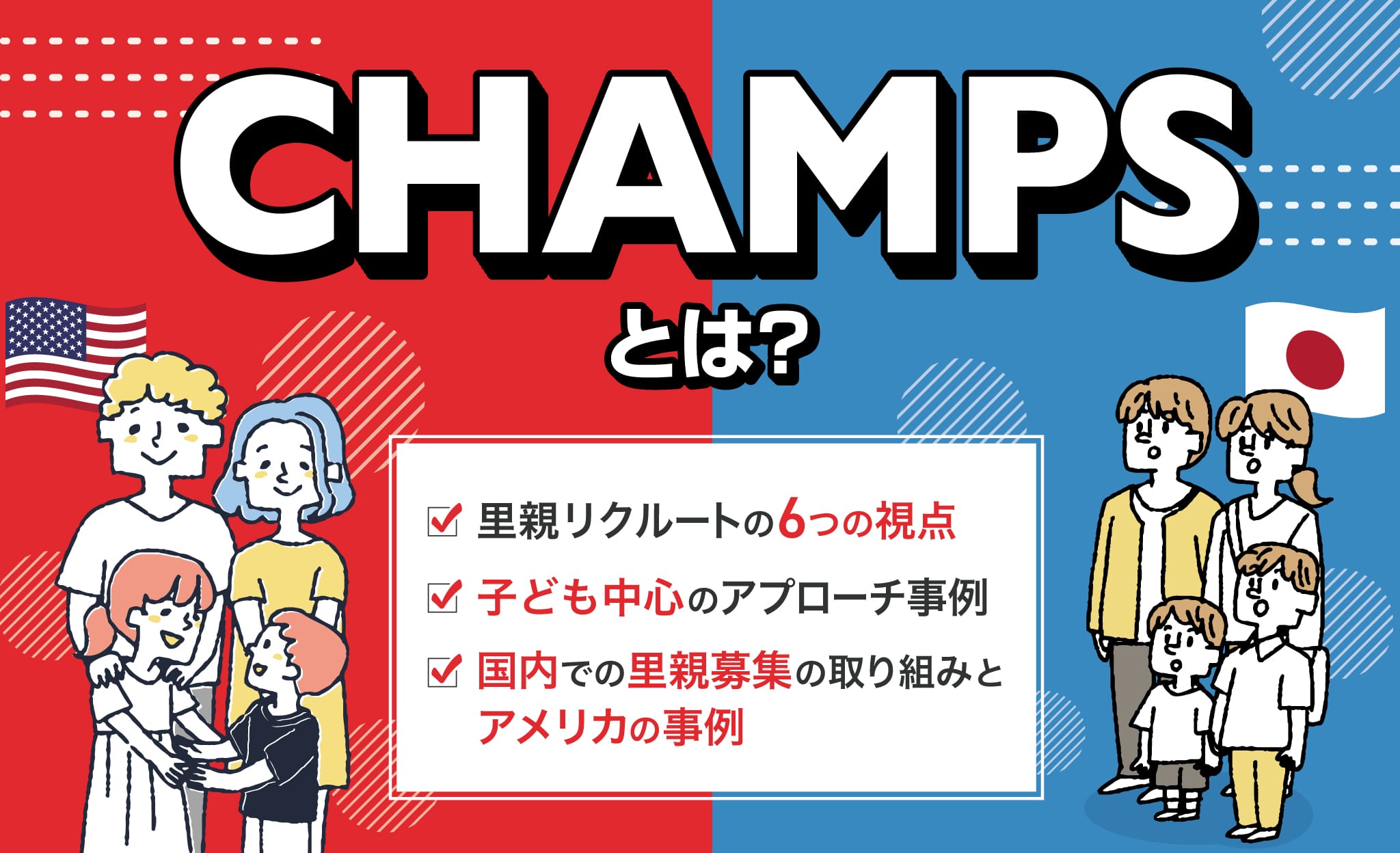子どもの社会問題
アドボケイトとは?用語の意味、制度の必要性、役割をわかりやすく解説
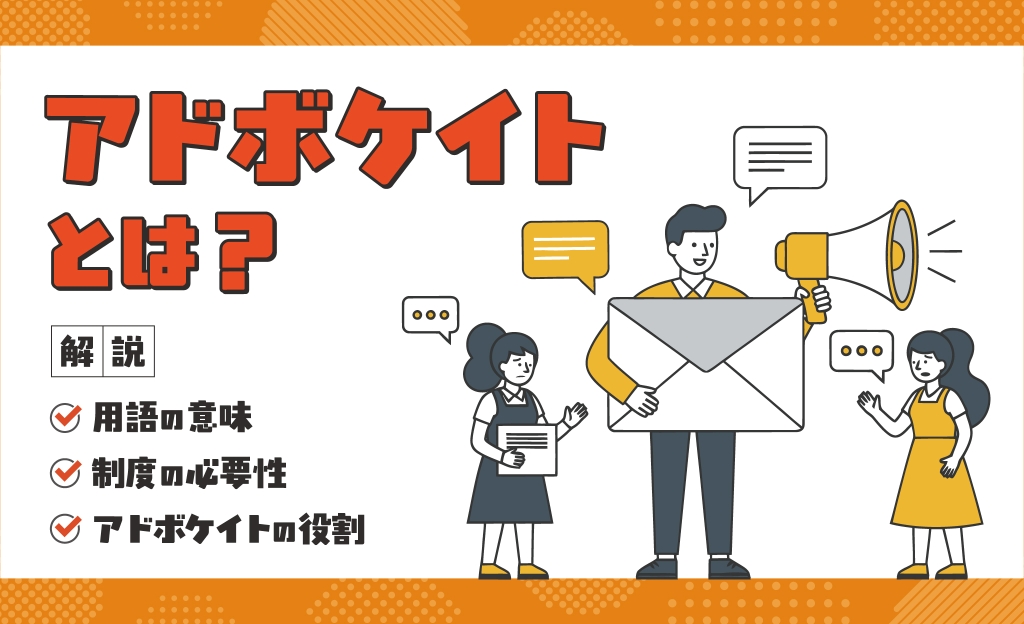
近年、アドボケイトの重要性を訴える声が大きくなってきています。
児童福祉の世界では、東京都目黒区の船戸結愛さん(5歳)や
千葉県野田市の栗原心愛さん(10歳)の虐待死事件が
痛ましい事件として広く知られています。
また、神奈川県では、虐待を受けていた中学2年生の男子が
十分な保護を受けられずに自殺してしまった事件が発生しました。
今後は、子どもの声の拡声器として機能するアドボケイトへの関心を
世の中全体で高めていかなければなりません。
そこで今回は、アドボケイトという用語の持つ意味や、
児童福祉上の役割・必要性、背景にある問題などをわかりやすく解説します。
アドボケイトとは
本来、アドボケイト(英語:Advocate)とは、
「権利表明が困難な子ども・寝たきりの高齢者・障害者など、
個々人の持つ権利をさまざまな理由で行使できない状況にある人に代わり、
その権利を代弁・擁護する人」を意味する言葉です。
弁護・支持・唱導・主張し、権利擁護のためにたたかうことであり、
由来は「To Call(声をあげる)」を意味するラテン語「voco」にあります。
児童福祉上のアドボケイトの例文を、以下に紹介します。
- ・アドボケイトという立場として、子どもに寄り添う。
- ・児童虐待の被害者を専門に扱うアドボケイトとして活動している。

アドボケイトの派生語
アドボケイトと類似する言葉の1つに、
アドボカシー(英語:Advocacy)が挙げられます。
これは、支援・介護などの対象者に代わり、
代理人・支援者などがその権利や意志を主張する行為そのものを意味する言葉です。
その権利を実現する機能のことを表すこともあります。
また、セルフアドボカシーという言葉もあります。
こちらは「自己権利擁護」とも呼ばれており、
障害などを持つ当事者自身が自身の権利や意思を主張し、
実現するために行う活動のことです。
児童福祉上の役割、必要性
児童福祉の分野には、さまざまな要因によって支援を必要としている子どもがいます。
これまでは、児童相談所などが福祉サービスを決定する際に、
子どもと親の双方の話を聞いて「子どもの最善の利益」は何かを考えて判断していました。
しかし、中には自分の意思をうまく言葉にできない小さな子供や、
障害を抱えていて自己主張ができない子どもも少なくありません。
また、児童虐待などの被害を受けながらもどう行動して良いのかわからない子どももいます。
こうした子どもたちが当たり前に持つ権利をきちんと守りつつ、
対象者の意見を尊重しながらその権利を行使できるように、
いわば「子どものマイク」となって周りの大人に子どもの意見を伝えていくのが、
アドボケイトの大切な役割です。

背景にある問題
アドボケイトの重要性が高まっている主な背景には、
児童虐待や子どもの貧困に関する問題が社会全体で認識されてきていることが挙げられます。
こういった報道などの影響もあり、
昨今は「児童虐待・子どもの貧困などに関する問題」が社会的に広く認知されてきました。
社会的な認知などを背景に、「アドボカシー」「アドボケイト」の
必要性を社会・行政としても取り上げなければならないと捉えた一部の自治体では、
具体的な施策として実施され始めています。

ガイドブックをシェアする
子どもの社会問題の関連記事
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える