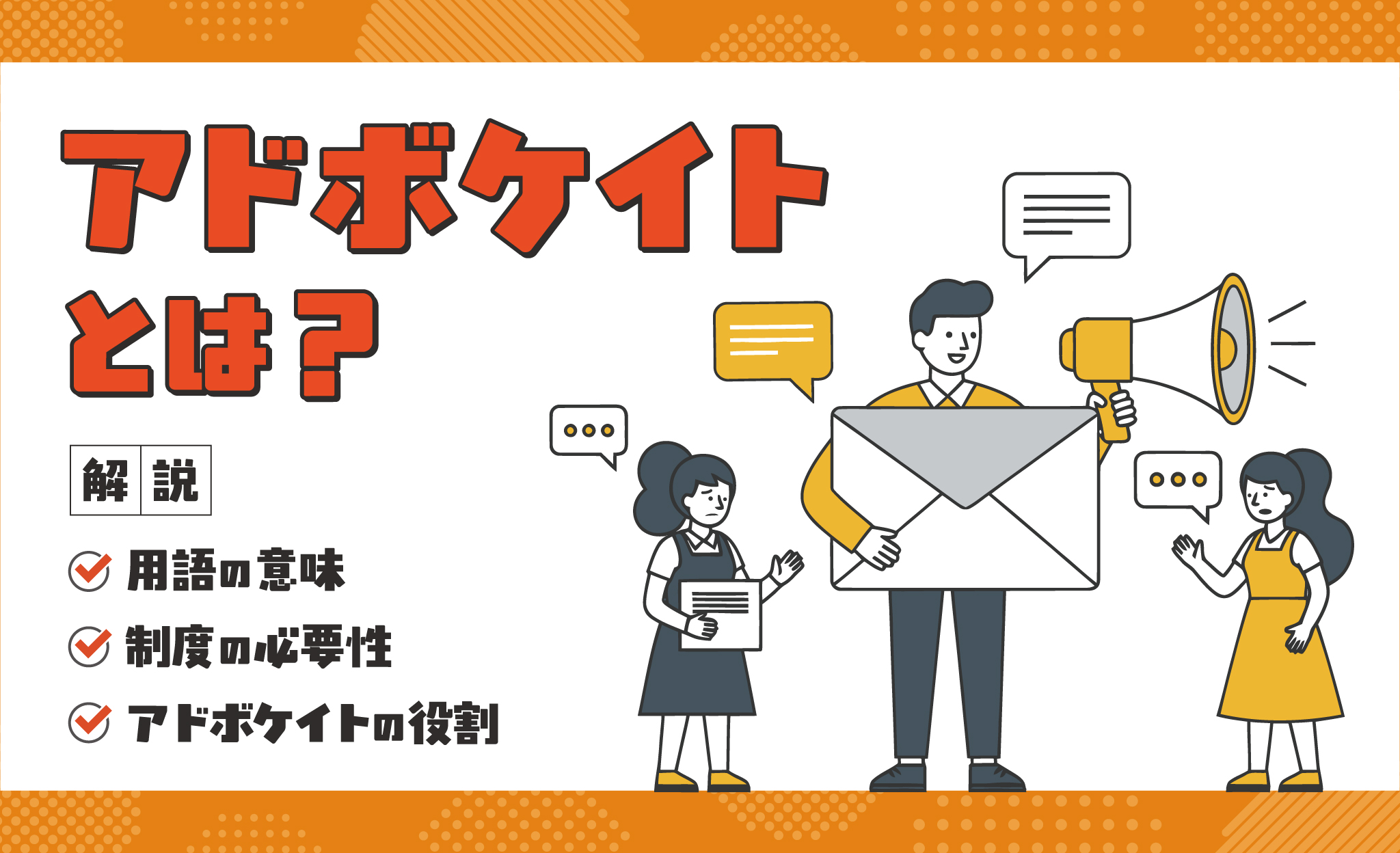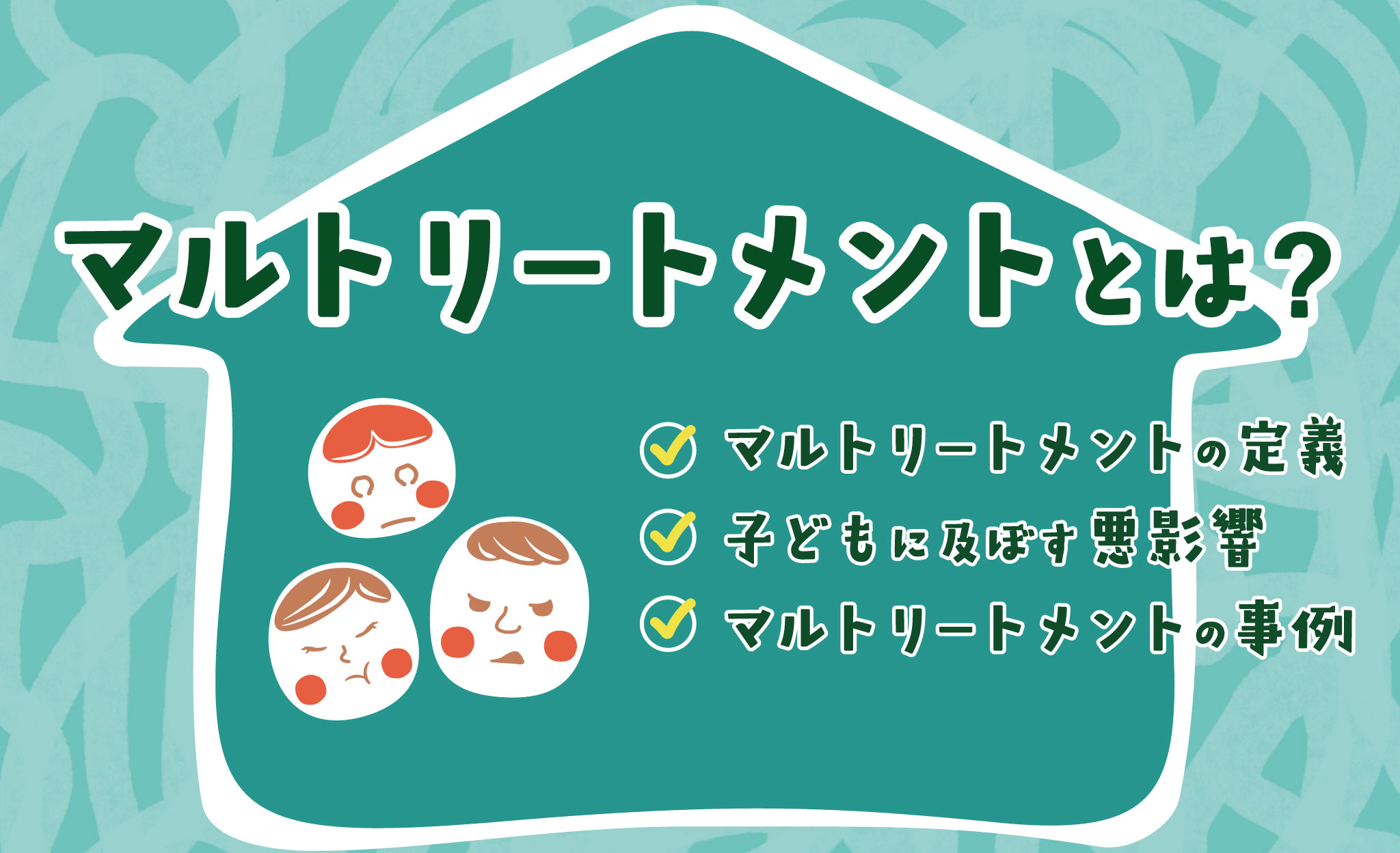子どもの社会問題
赤ちゃんポストとは?歴史や運営上の問題点も解説

親が育てられない子どもを匿名で預かる、いわゆる「赤ちゃんポスト」について、
東京都の墨田区の病院が、2024年度中の設置に向けて準備を進めている状況です。
今後は都や区と具体的な協議を進めていくとしています。
その一方で、北海道では、赤ちゃんポストを巡り、運営者と道の間で摩擦が生じています。
道は受け入れの中止を要請しましたが、運営者は孤立出産した人に「寄り添いたい」と
サービスを続けている状況です。
行政に監督や処分の権限がなく事態に進展は見られません。
そこで本記事では、赤ちゃんポストとはどういったものなのか、
言葉の意味の説明や運営上の問題点などを中心に解説します。

赤ちゃんポストとは
赤ちゃんポスト(Baby hatchまたはBaby boxとも呼ばれる)は、
育てることができない赤ちゃん(新生児や子ども)を親が匿名で託すことができる施設や
そのシステムのことで、日本での一般的な呼び名です。
赤ちゃんポストは、子どもの生命を守り、
特に困難な状況にある親が新生児を危険に晒さず安全に託せるように設置された施設です。
このシステムの主な目的は、新生児の命を救い、人工妊娠中絶や育児放棄、
さらには新生児殺害や遺棄といった犯罪を防ぐことにあります。
新生児は環境適応力が低く、無防備な状態で放置されると、野犬に襲われたり、
低体温症や熱中症で死亡したりするリスクが高いため、
これらの危険から赤ちゃんを保護するために設置されています。
日本では過去に、さまざまな理由から子どもを育てることができず、中絶を選択したり、
児童保護施設や慈善団体の前に子どもを置いて去ったりといったケースがありました。
これらの状況が時に新生児の命を失う悲劇を引き起こしていました。
このような事態を防ぐため、ドイツで始められた「ベビークラッペ」(赤ちゃんポストの原型)が、
赤ちゃんの命を救うための施設として世界に広がりました。
ただし、多くの国でこの制度が導入されているものの、
その運用や制度設計については十分な議論がされていないという問題が指摘されています。
赤ちゃんポストの歴史
日本では戦前から、育てることが難しい子どもを預ける施設が存在していましたが、
乳幼児の死亡事故が原因で閉鎖されることもありました。
現在は熊本県にある慈恵病院に「こうのとりのゆりかご」という名称の
公的に認められた赤ちゃんポストが設置されています。
これは日本で唯一の施設です。
この施設には人目を避けやすい位置に扉があり、その中にボックスが設置されています。
赤ちゃんをこのボックスに預けると、センサーが反応し、
医療従事者に通知される仕組みです。
預ける親は匿名であり、自分の名前を明かす必要はありません。
預けられた子どもは、まず医師によって健康状態がチェックされます。
その後、児童相談所が介入し、乳児院へ移送されます。
乳児院での一時的な保護を経て、子どもは施設で育てられるか、
適切な里親によって養子縁組されて家庭で育てられることになります。
赤ちゃんポストの問題点
2007年に設置された赤ちゃんポストには、設置から6年間で約100人の子どもが預けられました。
多くのケースでは経済的な困難や家庭環境の問題が理由ですが、
一部には「仕事中に子どもを預ける場所がない」「留学のため子どもを見ることができない」
といった、本来の目的と異なる理由で利用される事例もあります。
このような状況から、一部の親が軽はずみに子どもを手放すリスクも指摘されています。

ガイドブックをシェアする
子どもの社会問題の関連記事
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える