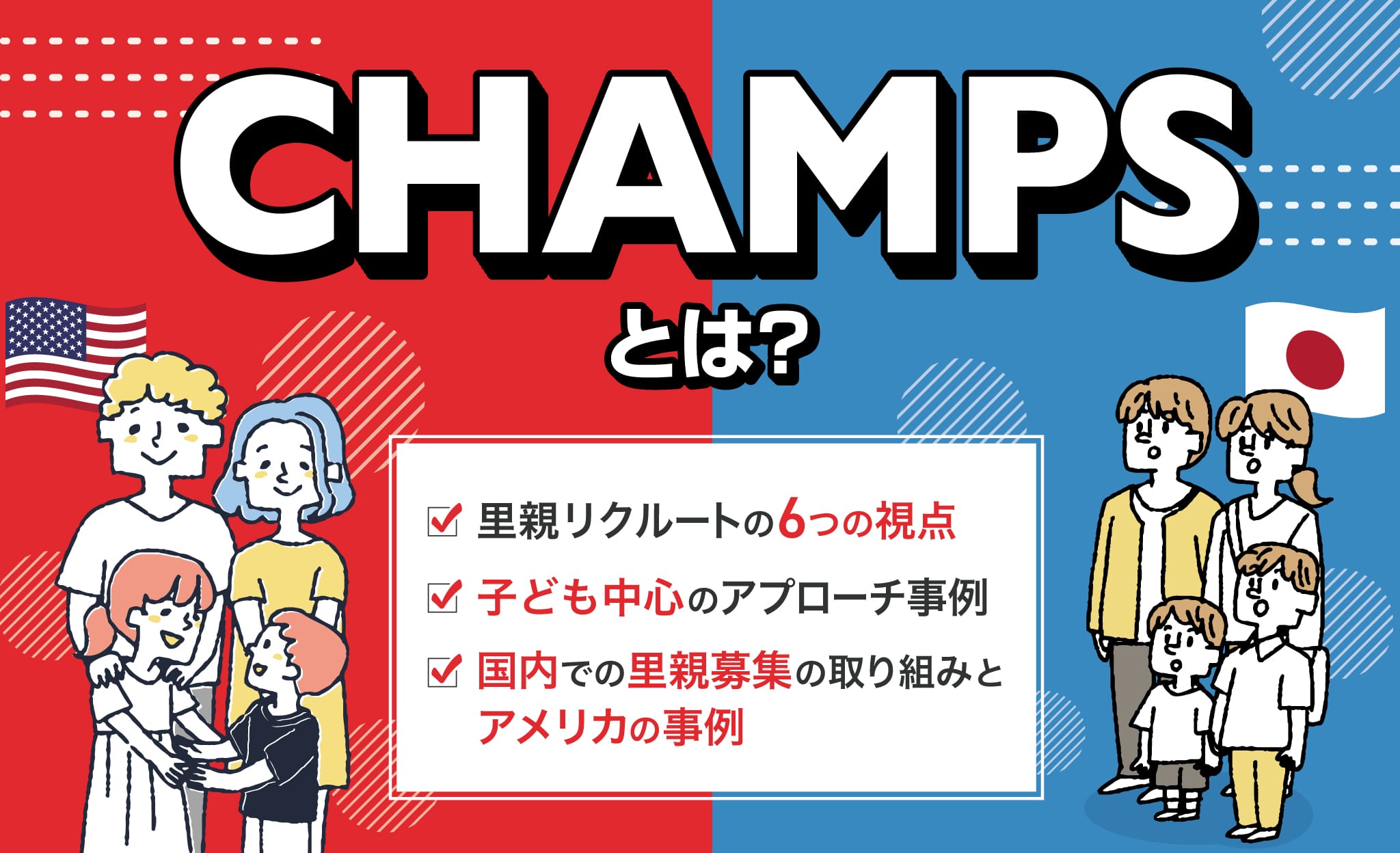子どもの社会問題
とも育てとは?マルトリの影響と予防に向けた取り組みについて解説

2024年10月12日から2日間にわたり、
福井県坂井市とあわら市で「第69回全国里親大会ふくい大会」
(兼 東海・北陸ブロック里親連絡協議会ふくい研修大会)が開催されました。
この大会には全国から里親や社会的養育に携わる関係者が集まり、
「広がれ里親の輪、応援します子どもの育ち」をテーマに
最新の知見を共有し、交流を深めました。
基調講演では、
福井大学子どものこころ発達研究センター教授の友田明美氏が
「子どもの脳を傷つけない子育て~マルトリートメント(マルトリ)
による脳への影響と回復へのアプローチ~」と題した講演を行いました。
友田氏は、子育てが困難な家庭で、
祖父母や地域の大人が親と協力しながら子育てを支える「とも育て」の重要性について言及し、「子どもへの避けたいかかわり=マルトリ」を防げることを強調しました。
本記事では、
マルトリの影響と予防に向けた取り組みとしての「とも育て」について解説します。
※「マルトリ予防」と「とも育て」はいずれも福井大学の登録商標です。
マルトリとは
マルトリ(マルトリートメント)とは、
虐待やネグレクト(育児放棄)を含む
「子どもへの避けたいかかわり」の全般を指します。
過度なしつけ、長時間の留守番、
異性の親との入浴、言葉の暴力なども含まれます。

子育てにおけるマルトリの影響
子どもがマルトリを受けると、
発達が「定型発達」から「非定型発達」に変化する場合があり、
ここにはASD(自閉スペクトラム症)や
ADHD(注意欠如・多動症)などの特性も含まれます。
しかし、環境要因により発達は改善する可能性もあり、
マルトリを防止することが大切であると考えられています。
マルトリは子育てと密接に関係しており、
愛着(アタッチメント)障害の原因となることもあります。
愛着障害は「育てにくい子ども(非定型発達)」に繋がり、
内向的な場合は無関心やイライラ、
適切な距離感が取れないなどの症状が、
外向的な場合は多動や友人関係のトラブルといった傾向が現れます。
こうした問題は、家庭での養育が難しいために
施設や里親に預けられた背景が関係していることが多く、
海外では19.4%から40.0%の子どもが愛着障害を抱えているとされています。

マルトリ予防手段としてのとも育て
友田氏が提唱するマルトリ予防策は、
社会全体で子どもを育てる「とも育て」の実現です。
根本には、「これから生まれてくる子どもは社会全体で育てる」
という視点を持つことが重要であるとの考えがあります。
近くに祖父母がいない場合でも、
保健センターや児童相談所、近所の住民、職場、
学校、幼稚園、保育所など、子どもに関わるすべての人が
「とも育て」の担い手となれます。
こうした「とも育て」の取り組みにより、
子育て中の親が孤立する「孤育て」を防ぐことが可能です。
また、マルトリートメントを行ってしまう親には、
親自身へのケアも必要です。
多くの場合、
こうした親たちは自分の幼少期に
過度なマルトリートメントを受けている可能性があります。
叩かれたり大声で怒鳴られたりする中で育った経験から、
同じ行動を繰り返してしまうことがあるのです。
こうした親御さんの心の傷を癒し、
サポートを行うことも、マルトリ予防には欠かせません。

ガイドブックをシェアする
子どもの社会問題の関連記事
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える