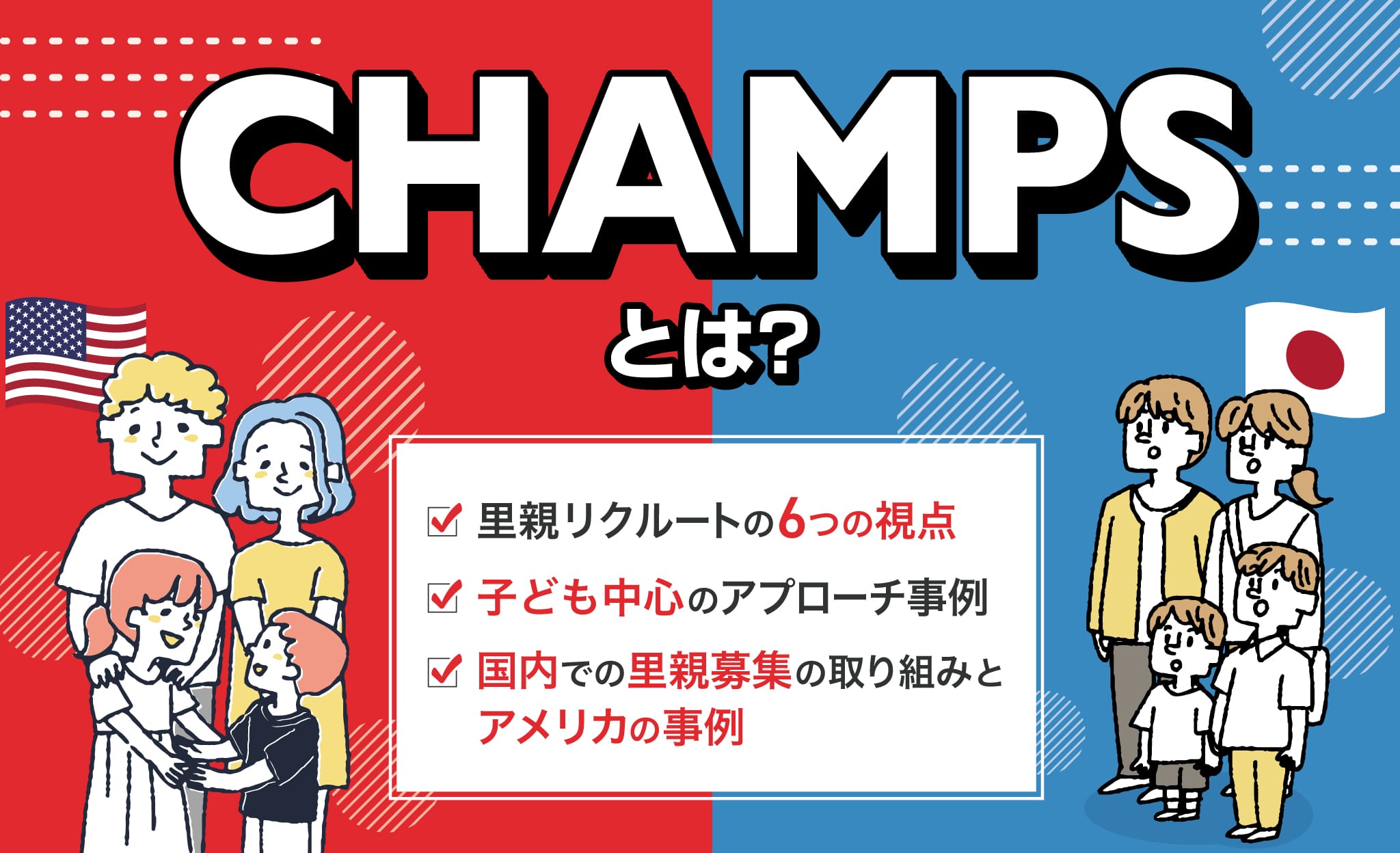里子との向き合い方
愛着形成とは?不十分だとどうなるか・愛着形成につながる取り組みを分かりやすく解説
最終更新日2025.04.03
公開日2025.04.03

愛着障害は、子どもが両親や他の養育者との間で健全な愛着関係を築けなかった結果として生じます。
これにより、大人になって対人関係や社会的な振る舞いに困難を持つ人も少なくありません。
愛着障害の問題の根底には、
愛着形成の段階での課題が存在することがしばしば指摘されています。
乳幼児期の心理的発展において、愛着形成はとても重要です。
愛着形成を通じて、子どもは他人を信頼する基礎を学び、
その後の感情的発達や人間関係の構築に深く影響を与えます。
この期間に健全な愛着形成を行っておくことは、子どもが将来、
社会性を身につけるうえで重要な基盤となります。
そこで本記事では、愛着形成の意味や不十分だとどうなるのかについて、
愛着形成につながる取り組みと併せて解説します。
これにより、大人になって対人関係や社会的な振る舞いに困難を持つ人も少なくありません。
愛着障害の問題の根底には、
愛着形成の段階での課題が存在することがしばしば指摘されています。
乳幼児期の心理的発展において、愛着形成はとても重要です。
愛着形成を通じて、子どもは他人を信頼する基礎を学び、
その後の感情的発達や人間関係の構築に深く影響を与えます。
この期間に健全な愛着形成を行っておくことは、子どもが将来、
社会性を身につけるうえで重要な基盤となります。
そこで本記事では、愛着形成の意味や不十分だとどうなるのかについて、
愛着形成につながる取り組みと併せて解説します。

愛着形成とは
「愛着形成」という概念は、
精神科医ジョン・ボルビィが1969年に発表した著書「愛着行動」で紹介されたものです。
子どもが不安を感じたときに、親や身近な信頼できる人に寄り添い、
安心を求める行動を指します。
実際に、小さな子どもは抱っこされることで安心し、
大人であっても不安や恐れを感じるときは誰かのそばにいることで落ち着くことがあります。
この自然な反応がまさに愛着形成です。
愛着形成は、
子どもが反復して特定の人(例:保護者や保育士)との安心できる関係を築くことによって、「安全基地」としての認識を深めるプロセスです。
子どもは、この「安全基地」が存在することで安心感を持ち、
心が安定し、健全に成長できます。
愛着形成が完了するのは、おおよそ2歳から3歳頃とされています。
この期間に形成された愛着は、子どもの将来の人間関係の基盤となります。
精神科医ジョン・ボルビィが1969年に発表した著書「愛着行動」で紹介されたものです。
子どもが不安を感じたときに、親や身近な信頼できる人に寄り添い、
安心を求める行動を指します。
実際に、小さな子どもは抱っこされることで安心し、
大人であっても不安や恐れを感じるときは誰かのそばにいることで落ち着くことがあります。
この自然な反応がまさに愛着形成です。
愛着形成は、
子どもが反復して特定の人(例:保護者や保育士)との安心できる関係を築くことによって、「安全基地」としての認識を深めるプロセスです。
子どもは、この「安全基地」が存在することで安心感を持ち、
心が安定し、健全に成長できます。
愛着形成が完了するのは、おおよそ2歳から3歳頃とされています。
この期間に形成された愛着は、子どもの将来の人間関係の基盤となります。
愛着形成が不十分だとどうなるか
愛着形成がうまくいかなかった人の場合、
好奇心や積極性、自己肯定感が適切に育まれておらず、
進学や就職などの決断に苦労することがあります。
また、それに伴ってアイデンティティの確立ができず、
自分の存在価値について悩み、自己肯定感が低下するというケースが多いです。
また、情緒面や対人関係の面で以下のような特徴が見られることもあります。
・ちょっとしたことで傷つきやすい
・怒ると建設的な話し合いができない
・過去の失敗や恐怖をいつまでも引きずる
・「好き」か「嫌い」か、「ある」か「ない」かの2択しかない
・折り合いをつけることができない
・養育者との関係が悪い
・人との適切な距離感がわからない
・恋人や配偶者、自分の子どもの愛し方がわからない
好奇心や積極性、自己肯定感が適切に育まれておらず、
進学や就職などの決断に苦労することがあります。
また、それに伴ってアイデンティティの確立ができず、
自分の存在価値について悩み、自己肯定感が低下するというケースが多いです。
また、情緒面や対人関係の面で以下のような特徴が見られることもあります。
・ちょっとしたことで傷つきやすい
・怒ると建設的な話し合いができない
・過去の失敗や恐怖をいつまでも引きずる
・「好き」か「嫌い」か、「ある」か「ない」かの2択しかない
・折り合いをつけることができない
・養育者との関係が悪い
・人との適切な距離感がわからない
・恋人や配偶者、自分の子どもの愛し方がわからない

愛着形成につながる取り組み
愛着は、子どもが周囲の世界と適応するための本能的な感情や行動です。
人間の子どもは非常に脆弱で、
自分を守るために信頼できる大人との情感的な繋がりを求めます。
このため、親の反応は子どもの性格形成に重要な役割を果たします。
愛着を育むための有効な方法を紹介します。これらを習慣にしましょう。
- ・授乳やミルクをあげる際には、子どもの目を見て、優しく話しかける
- ・毎日、「大好きだよ」「かわいいね」と愛情の言葉を伝える
- ・ベビーマッサージや触れ合い遊びを日常的に行う
- ・子どもが他人に慣れる過程を肯定的に捉え、喜ぶ
- ・言葉を理解し始めたら、子どもの要求に笑顔で応じる

これらの取り組みを行う際、特別なスキルは不要で、
ただ愛情を持って子どもと接することで自然に実践できます。
子どもが安心感に満ちた環境で成長することで、探求心や冒険心を後押しできるでしょう。
ただ愛情を持って子どもと接することで自然に実践できます。
子どもが安心感に満ちた環境で成長することで、探求心や冒険心を後押しできるでしょう。
ガイドブックをシェアする
里子との向き合い方の関連記事
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える