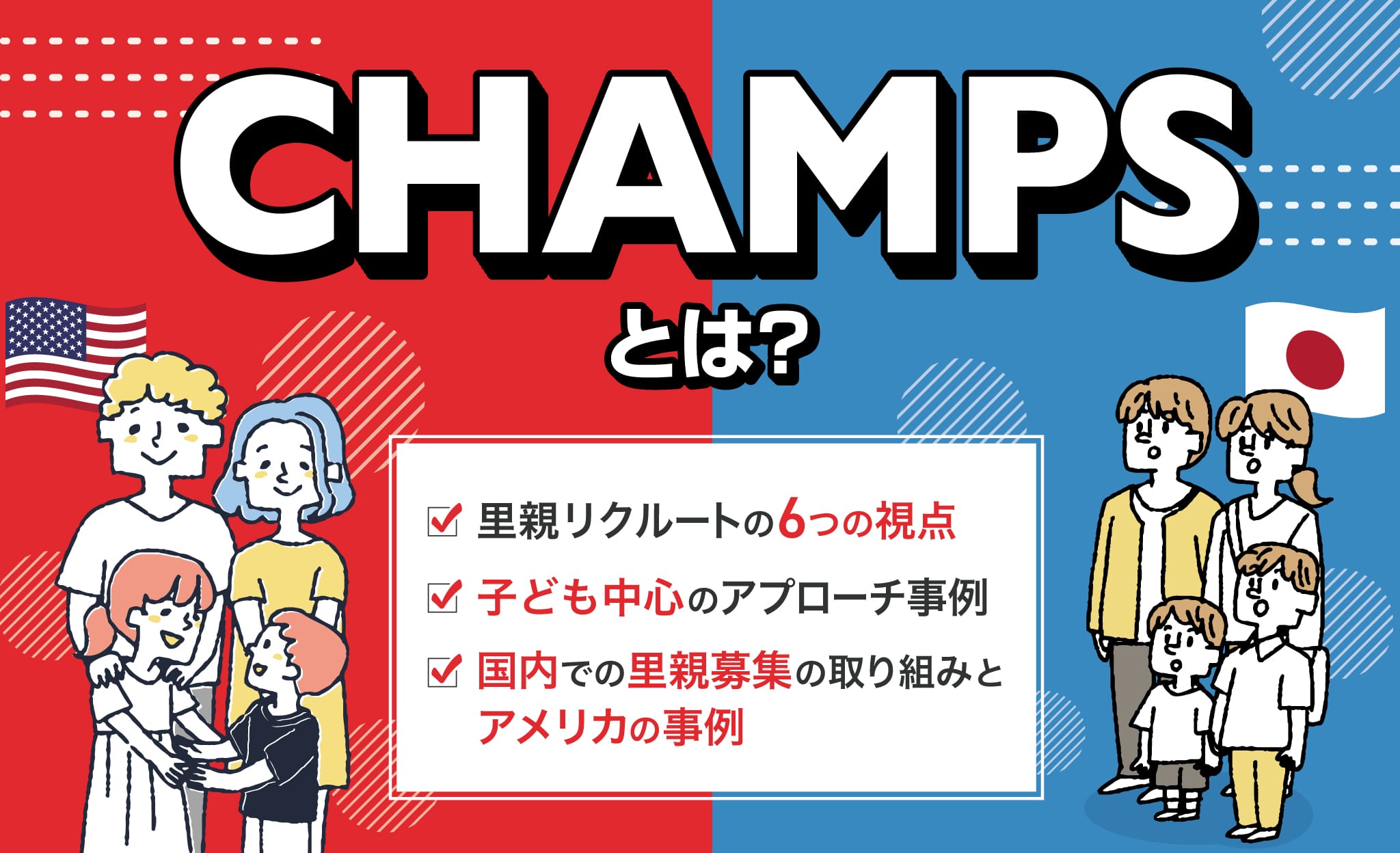子どもの社会問題
ヤングケアラーとは?日本現状や問題点、相談窓口も紹介

ヤングケアラーのことについて、どれだけご存じあるでしょうか?
ヤングケアラーとは、家族の介護やケア、
身の回りの世話を担う18歳未満の子どものことです。
その生活が当たり前であり、
自身がヤングケアラーだという認識がない子どもも少なくありません。
そこで本記事では、
まずは実態を知ってほしいという考えから、
ヤングケアラーの概要や日本現状、抱える問題点や
主な相談窓口などをわかりやすくまとめました。
ヤングケアラーとは
ヤングケアラー(英語: young carer)とは、
病気や障害のある家族・親族の介護・面倒に忙殺されており、
本来受けるべき教育を受けられなかったり、
同世代との人間関係を満足に構築出来なかった子どもたちのことです。
大人が担うようなケアの責任を引き受け、
家族の世話全般(例:家事、介護、感情面や家計支援のサポート)を行っている
18歳未満の子どもをさします。
その子どもがケアしているのは、
主に障害や病気のある親や高齢の祖父母、兄弟姉妹といった親族であることが一般的です。
なお、日本では、ヤングケアラーの法律上の定義は存在せず、
研究者等の定義から18歳未満の子どもとされるのが一般的ですが、
一般社団法人日本ケアラー連盟は、これに加えて
18歳~おおむね30歳代までのケアラーを「若者ケアラー」と定義しています。

日本の現状
三菱UFJリサーチ&コンサルティングが取りまとめた
報告書「ヤングケアラーの実態に関する調査結果」によると、
中学2年生の約17人に1人がヤングケアラーであることがわかっています。
しかし、ヤングケアラーと自覚している子どもは約2%しかいません。
わからないと答えている中学2年生は12.5%おり、
ヤングケアラーに該当しているかわからないままケアをしている現状が
浮き彫りになっています。
そもそもヤングケアラーという言葉自体の認知度も低く、
聞いたことがないと答えた人が8割を超えています。
この報告書からは、幼い頃から介護が日常にあるために、
無自覚のまま負担がかかっており、
助けを求められない子どもが多くいると推察できます。
問題点
ヤングケアラーである子どもにとっては、
手伝いの域を超える過度なケアが長期間続けば、
心身に不調をきたしたり遅刻や欠席が多くなったりして、
学校生活に深刻な悪影響が及ぶおそれがあります。
進学・就職を断念するなど、
子どもの将来を左右してしまう事例も問題視されています。
その他の問題点を以下に列挙しました。
- ・交友関係が希薄になりやすい
- ・睡眠不足や生活リズムが崩れるなど健康が損なわれる
- ・虐待・自傷行為など身体に危険が及ぶおそれ
- ・家庭崩壊や地域社会からの孤立
ヤングケアラーの子どもの存在が問題視されているにもかかわらず、
行政側の支援はまだ十分とは言えません。
政府自治体に対して実態調査を勧めるように促していますが、
多くの自治体で調査予定が決まっていない状況です。
なぜなら、ヤングケアラーの支援には、
福祉、教育などさまざまな観点からのフォローが必要であり、
管轄する部署が複数に渡ることから、調整に苦戦しているためです。
貧困家庭などの問題に比べて外部から発見しにくく、
そもそも支援が必要なヤングケアラーの把握が難しい点も課題です。

主な相談窓口
ヤングケアラーに関する相談窓口には、主に以下のようなものがあります。
児童相談所相談専用ダイヤル
児童相談所は、都道府県、指定都市等が設置する機関で、
子どもの健やかな成長を願って、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。
虐待の相談以外にも子どもの福祉に関する様々な相談を受け付けています。
- 電話番号:0120-189-783(フリーダイヤル)
- 受付時間:24時間受付(年中無休)
- 24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)
いじめやその他の子供のSOS全般について、
子供や保護者などが夜間・休日を含めて24時間いつでも相談できる、
都道府県及び指定都市教育委員会などによって運営されている、
全国共通のダイヤルです。
- 電話番号:0120-0-78310(フリーダイヤル)
- 受付時間:24時間受付(年中無休)
- 子どもの人権110番(法務省)
いじめや虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
- 電話番号:0120-007-110
- 受付時間:平日8:30~17:15 ※土・日・祝日・年末年始は休み

ガイドブックをシェアする
子どもの社会問題の関連記事
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える