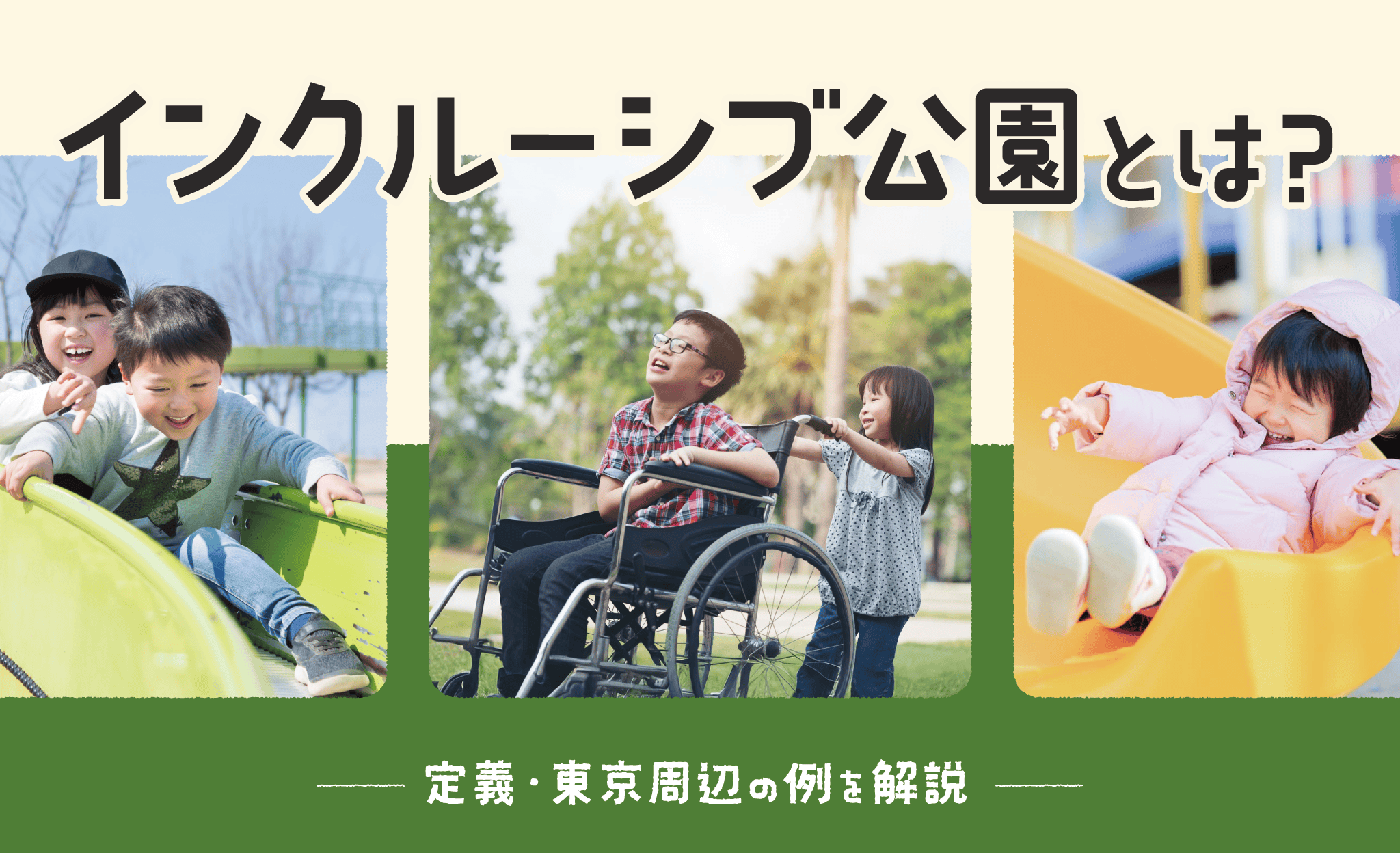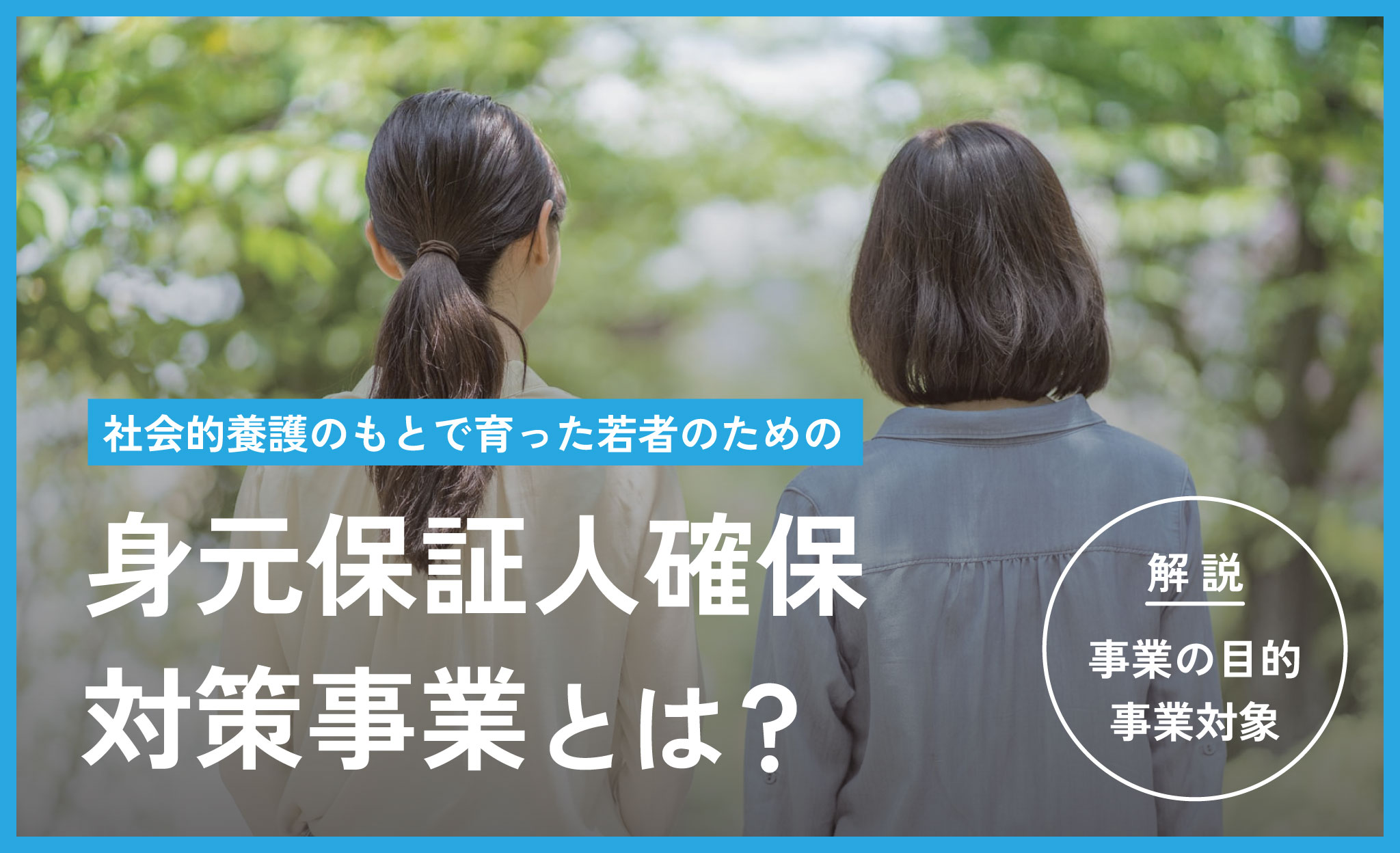医療
アウトリーチとは?社会福祉分野での意味、基礎知識を紹介
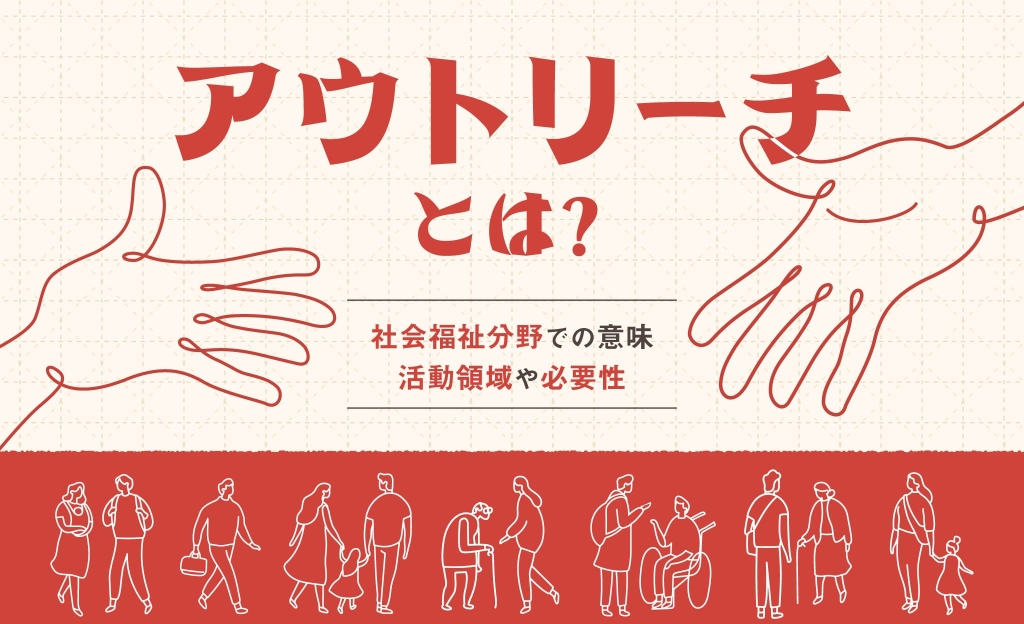
近年、日本各地の文化施設で、
アウトリーチ活動が盛んになっています。
アウトリーチとは、もともと「手を伸ばすこと、伸ばした距離」や
「(地域への)奉仕・援助・福祉活動」
「(公的機関や奉仕団体の)出張サービス」などを意味する言葉です。
一般的に、
生活困窮者は自身でSOSを発することが難しいケースが多いです。
そのため、
積極的に対象者を発見するための「アウトリーチ」が必要とされます。
なるべく早期に生活困窮者を発見できることが望ましいでしょう。
そこで今回は、アウトリーチ活動に興味のある人に向けて、
社会福祉分野での用語の意味や概要、必要性や近年の動向などをわかりやすくまとめました。
アウトリーチとは
アウトリーチ(英語:Outreach)とは、
「手を伸ばすこと」を意味する英語から派生した言葉で、
公的機関や文化施設などによる地域への出張サービスのことです。
医療分野などでは、
地域に溶け込む必要性がある開業医が往診などをすることをさします。
また、美術館・博物館が裾野を広げる契機として
施設訪問など対外的な広報活動をすること、
マイノリティの人々が自らの存在を周知させるための活動をさすこともあります。
そのほか、地方自治で住民主体のまちづくりの取り組みが盛んになりつつあるなか、
まちづくりに対する地域住民の声を収集したり、
関心を高めたりする活動をアウトリーチと呼ぶこともあります。
アウトリーチの対象は、
支援を不要だと拒んでいる人(困り感がない、感じにくい状況にある。
改善すると思えない、諦めている。支援者や社会に対する不信感がある。)や
心身の不調・障害等で来所することが難しい人(
身体障害があり外出が難しい。体調が悪く、外出が難しい。
精神疾患があり公共交通機関を使うのが難しい。
対人不安・恐怖があり、人が多いところに出てくるのが難しい。)などです。

社会福祉分野での意味
社会福祉分野において、アウトリーチは、
支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対して、
行政や支援機関などが積極的に働きかけて情報・支援を届けるプロセスを意味する言葉です。
活動領域
アウトリーチが実施されている領域は、
福祉分野のなかでも多岐にわたります。
例えば、在宅医療・往診・看護など病気を持っていても
通院が困難な人に向けて、地域や自治体の保健師が行うことがあります。
また、NPOや市民団体も相談援助につなげるためのアウトリーチを実施している状況です。
路上でホームレス状態にある人に声をかけたり、
家出している若者に向けて声をかけたりする「夜回り活動」などが代表例です。
こうしたアウトリーチ活動を通じて、
生活課題を抱えながら福祉の支援を受けていない人に情報を届けながら、
自団体や公的機関などの支援を通して
生活課題を解決する取り組みがみられます。
そのほか、ひきこもり支援や災害対策、
児童虐待予防、自殺対策など地域福祉の多様な領域で行われている状況です。

必要性
近年、さまざまな分野でアウトリーチの必要性が認識され、
その内容は広がりをみせています。
具体例を挙げると、ニートや引きこもりの若者に対する家庭訪問、
子育ての孤立感や不安感の解消を目指す子育て支援、
精神的不調を抱える人に対して
精神疾患の悪化や自殺を予防するための訪問支援などが代表的です。
また、待っているのではなくこちらから手を差し伸べるアウトリーチの手法は
芸術分野でも活用されており、音楽では公共ホールが学校や地域にプロの演奏家を派遣して、
ミニコンサートやワークショップを開催する動きも活発化しています。
このような出前コンサートは、ひいては音楽に関心のある層を増やし、
公共ホールの活性化にもつながります。

ガイドブックをシェアする
医療の関連記事
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える