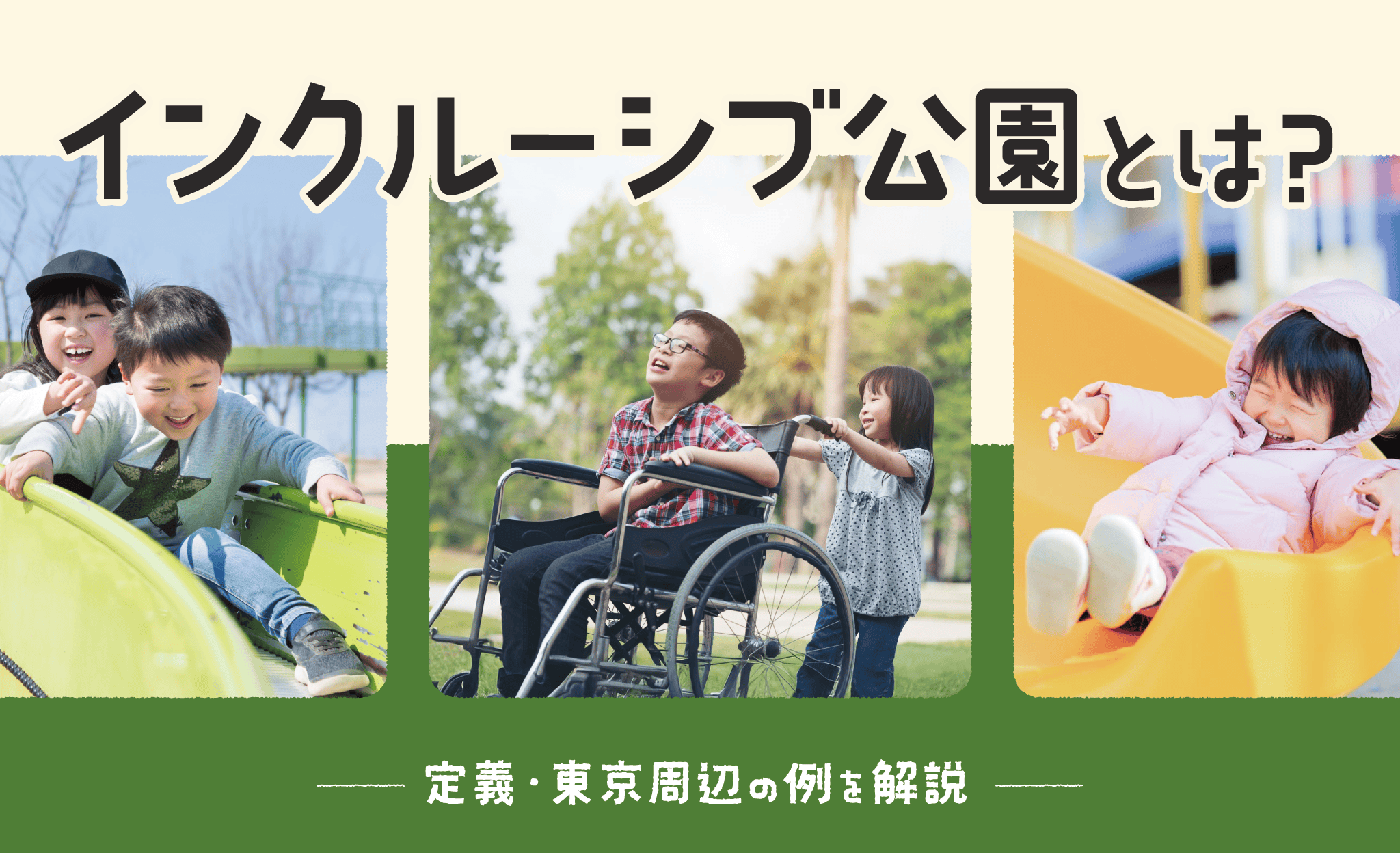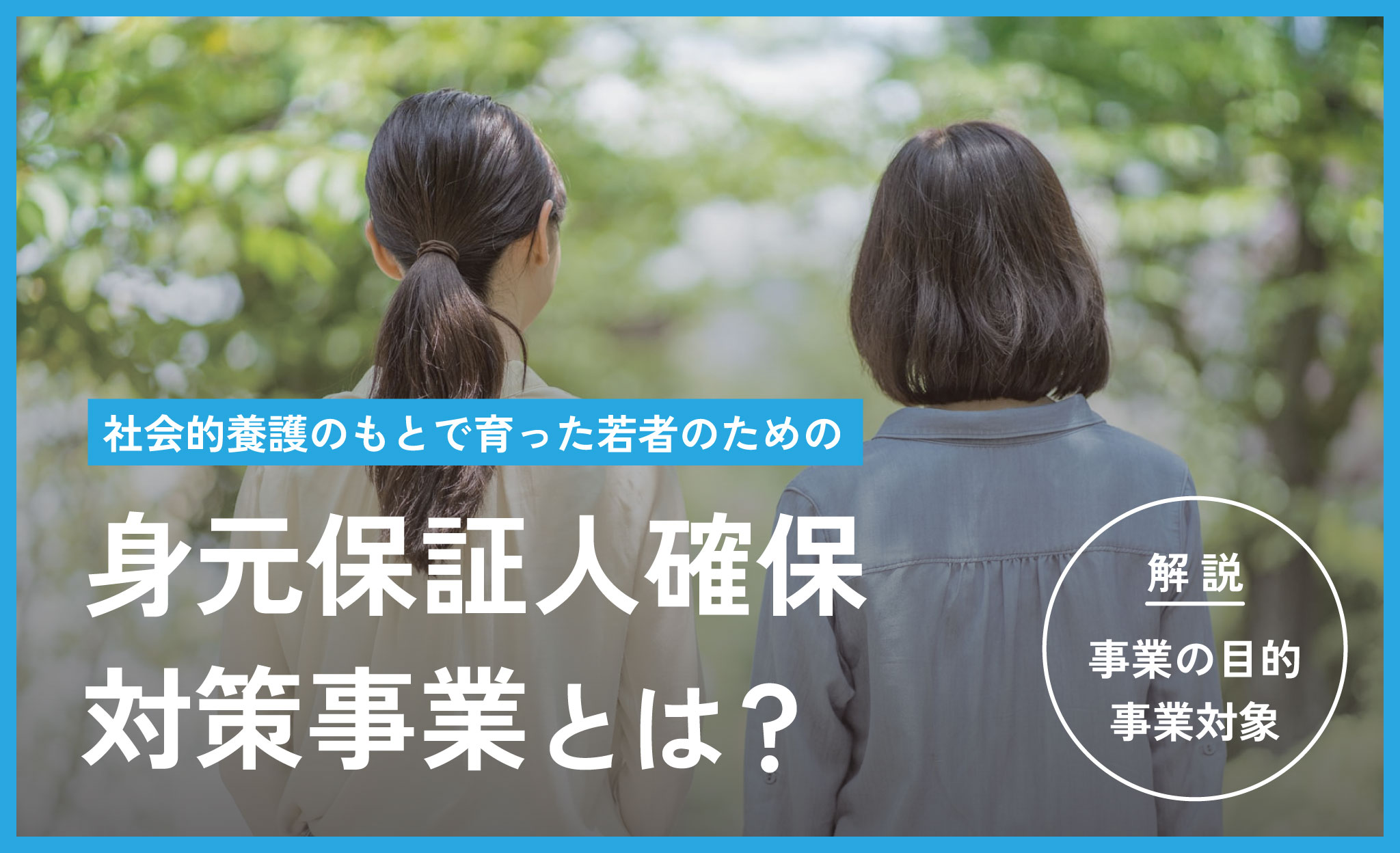里親を支える
インクルーシブ公園とは?定義、東京近郊の例を解説

インクルーシブとは、
日本語で「包み込むような、包摂的な」を意味します。
英語で「除外(Exclude)」の対義語である「Include(含める)」が語源で、
誰も排除しない社会を目指す考え方です。
従来の社会のあり方は、
性別・人種・民族・国籍・出身地・社会的地位・障害の有無などによって、
多くの人々を分け隔ててきました。
しかし、昨今は「誰一人取り残さない」をテーマに掲げるSGDs達成に向けて、
インクルーシブな考え方をさまざまな場面で採り入れる動きが社会全体で広がっています。
インクルーシブ公園の導入も、
この動きの一環として位置付けられます。
そこで今回は、インクルーシブ公園の定義や重要性、
実際にある公園の一例などを幅広く解説します。
インクルーシブ公園とは
インクルーシブ公園とは、障がいの有無にかかわらず、
あらゆる子どもが家族や友達などと安全・快適に遊べるよう設計・整備された公園のことです。
社会的に弱い立場にある人々を含むすべての人を受け入れ、
支え合うという理念にもとづいています。
例えば、段差のない設計や車いすに乗ったまま遊べる遊具の設置など、
ユニバーサルデザインの視点を取り入れた公園づくりがなされています。
近年は欧米だけでなくアジア諸国でも設置が広がっており、
日本では2020年に東京都内に2つの同公園が設置され、
他の自治体でも導入に向けた検討が行われている状況です。
具体的に、インクルーシブ公園と普通の公園の違いを説明するために、
東京都建設局の「だれもが遊べる児童遊具広場」のガイドラインを参考にすると、
例えば、インクルーシブ公園の利用を想定しているのは
3~6歳の幼児と6~12歳の小学生で、その親・介添者・兄弟なども含みます。
そして、ユニバーサルデザイン、
つまり「だれもが同じように」「容易に」「危険なく」「使い勝手よく」「気持ちよく」という5つの視点をもとに整備されている点に特徴があります。
参考:東京都建設局「だれもが遊べる児童遊具広場の整備」

重要性
街中にある公園は市民に開かれている公共施設ですが、
通常の公園では思うように遊べていない子どもも少なからず存在します。
障害のある子を持つ親からは、障害があることで公園を利用できず、
友達や家族と一緒に遊べないという意見が多く挙がっています。
こうした声を拾い上げて、
障がいがあってもなくてもみんなで一緒に遊べる場を提供する施設として、
インクルーシブ公園の重要性が高まっている状況です。
東京近郊のインクルーシブ公園の一例
東京近郊のインクルーシブ公園の一例を下表にまとめました。
| 名称 | 概要 |
| 雑司が谷公園 | ・視覚、聴覚、触覚で遊べるプレイビルダーというインクルーシブ遊具が設置されている
・車いすに乗ったままでも遊べる |
| 駒込七丁目第2児童遊園など |
・回転遊具「オムニスピナー」というインクルーシブ遊具が設置されている ・回転スピードがゆるやかで、内向きに座るため子どもの表情を常に確認できる ・車いすから乗り移りやすいよう低く設計されている |
| としまキッズパーク |
・事前予約制 ・キッズハウス、おやこブランコ、おやこすべり台、すなばなど、さまざまなインクルーシブ遊具が揃っている |
| 恵比寿南二公園 | ・大きな座面と手すりのあるシーソーが設置されている |
| 二子玉川公園 | ・車いす用の砂場が設置されている |
| 都立砧公園 |
・障がいがある子もない子も世代・国籍を超えて誰でも一緒に遊べる遊具広場「みんなのひろば」が設置されている |
| 秋葉台公園 |
・2021年3月、神奈川県で初めて障がいの有無に関係なく子どもたちが一緒に遊べるように設計された「トリム広場」が設置された |

ガイドブックをシェアする
里親を支えるの関連記事
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える