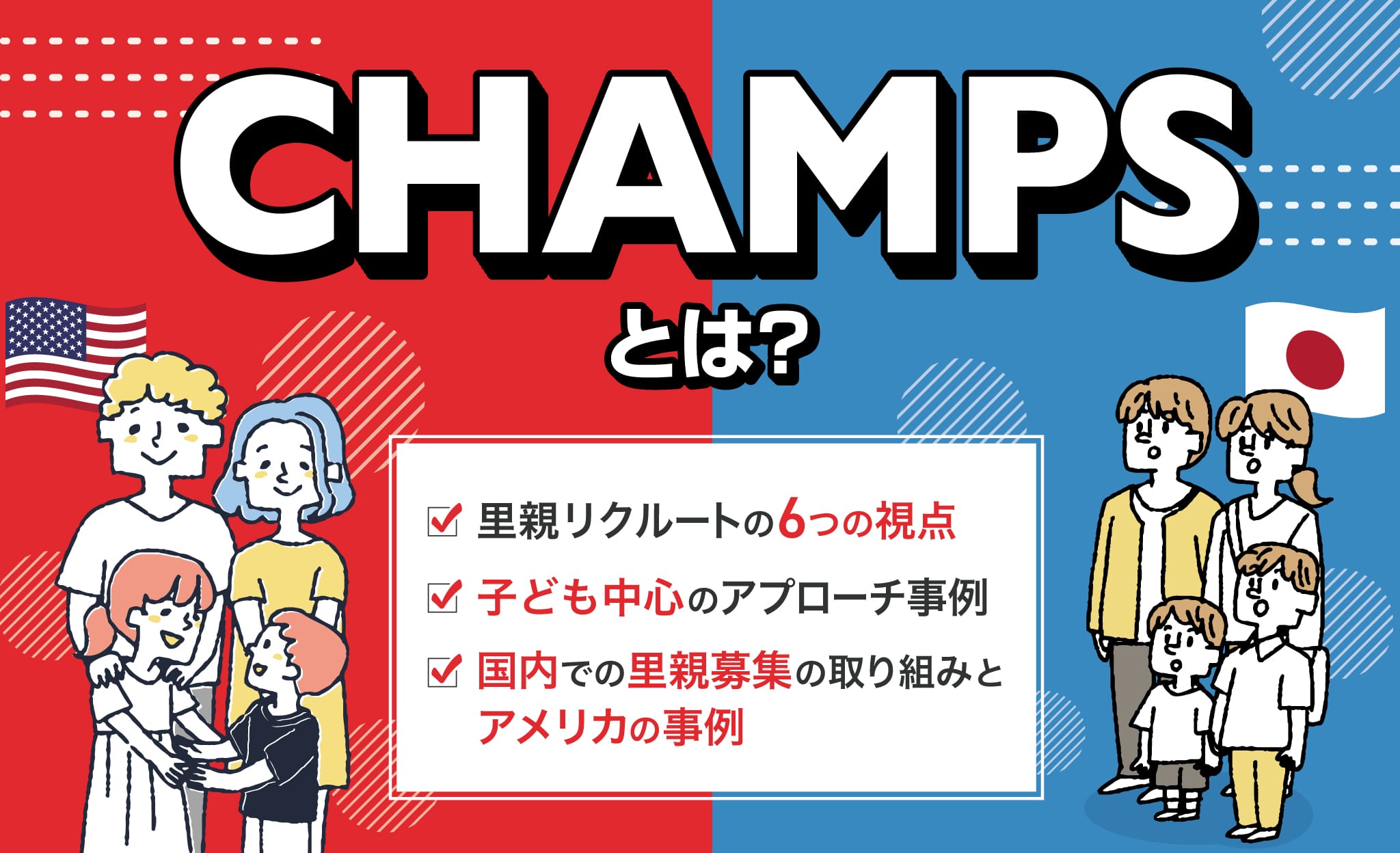里子との向き合い方
保育におけるアタッチメントとは?用語の意味や重要性・形成する方法を解説

保育や子育てをしていると「アタッチメント」という言葉を見聞きすることがあるかと思います。「愛着」や「愛着関係」を意味する言葉かな?とイメージする方も多いはず。
アタッチメントは、子どもの成長段階においても、社会性の基となるとっても大事な要素です。知識があれば、子ども達のSOSや必要な成長を促す指針になるでしょう。
そこで本記事では、保育におけるアタッチメントとはどういったことを意味するのか、重要性や形成する方法と併せて解説します。
保育におけるアタッチメントとは
「アタッチメント(Attachment)」とは、
日本語で「付着」や「連結」などと訳される言葉です。
もう少し簡単に説明すると、「くっつく」「しがみつく」を意味する言葉で、
小さな子どもが大好きな大人にぴったりとくっついている姿を思い浮かべる方もいるでしょう。
保育におけるアタッチメントとは、論者によって解釈が多少異なりますが、
多くの場合は「情緒的な絆」や「愛着関係」などを意味します。
アタッチメントは、保育や幼児教育においてとても大切な概念です。
しかし、
核家族化が進む現代の日本では親子のアタッチメントが健全に築かれないケースもあり、
そのことが後々になって子ども世代の心理的問題に発展することもあり、
大きな社会問題になっています。

アタッチメントを形成する大切さ
アタッチメントが十分に形成されている子どもは、
安心感のある大人のそばから積極的に外の世界に目を向け、
さまざまなことに興味を持ち、新しい挑戦を始められるようになります。
つまり、アタッチメントの形成は、
子どもの自我の成長や自己肯定感を育む上で非常に重要な役割を果たすのです。
0歳から2歳の乳幼児期においては、信頼できる大人との感情的な結びつきを築くことが
特に大切です。
簡単にいえば、子どもたちの感情的な欲求が満たされ、
彼らの「抱っこしてほしい」という気持ちに寄り添うことができるかが、
日々の保育における重要なポイントです。
毎日、一人ひとりの子どもと心をこめて向き合うことが、
彼らの健やかな成長につながります。

アタッチメントの形成が不十分な子どもに見られる特徴
アタッチメントの形成が不十分な子どもは、
人との関係性を築くことが難しくなる傾向があります。
以下のような振る舞いがその一例です。
- ・他人とのやりとりで適切に反応できない
- ・他人に対して過剰に警戒し、関わりを避けがちになる
- ・自尊心が低く、怒りやすい、あるいは簡単に落ち込む
- ・相手に喜んでもらおうとして、過度に頑張ってしまう
- ・他人との適切な距離感がつかめず、近づきすぎることがある
- ・警戒心が薄く、知らない人ともすぐに話してしまう
これらの行動は保育園などでよく見られるものですが、
必ずしも発達障害を意味するわけではありません。
ただ、これらの特徴は発達障害の特性に似ているため、
注意深く観察し、適切な支援を考える際の一つの手がかりとなり得ます。
アタッチメントを形成する方法
保育所保育指針によれば、乳児期の子どもたちは両親や保育者など、
彼らにとって身近な大人とのやりとりを通して、情緒的なつながりを築いています。
このような大人と子どもとの関わりは、子どもが感じる不安や欲求を解消する重要な手段です。
例えば、眠いときや寂しいときに、子どもたちは言葉にできないながらも
「抱っこしてほしい」というサインを泣くことで示すことがあります。
こうしたとき、子どもの要求に応えて抱きしめるなどの対応をすることで、
子どもは安心感を得ます。
これを繰り返すことで、子どもは特定の大人に対する愛着、
すなわちアタッチメントを形成していきます。
子どもの欲求に対して身近な大人が応じることが、子どもの心の安定にとってとても重要です。
ガイドブックをシェアする
里子との向き合い方の関連記事
“心の支え”となるコミュニティ
ONE LOVE オンライン里親会は、里親が抱える日々のつらさやしんどさ、喜びを共有できるコミュニティとしてすべての里親をサポートします。

オンライン里親会は、無料で参加いただけます
メンバー登録をするはじめて知った里親の方へ
ONE LOVE オンライン里親会とは里親や次世代の子どもを支えたい方へ
寄付で支える